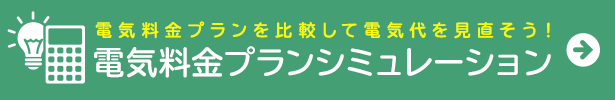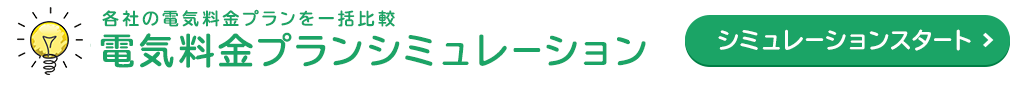電力自由化
更新日:2024年04月17日
家庭向け(低圧)は企業向け(高圧・特別高圧)の3倍以上?

託送料金とは?
電力小売りの全面自由化開始までは、一般電気事業者と言われる東京電力や関西電力など地域の大手電力会社が、発電から送配電、小売りまでを一貫して一社で行い、一般家庭を含めた管轄地域すべての電力需要に対して責任を持って供給するという法規制のもとで電気事業を行ってきました。電力の供給システムは、大きく発電部門、送配電部門、小売部門の3つに分類されますが、電力小売りの全面自由化後はそれぞれの部門を発電事業者、送配電事業者、小売電気事業者が別々に手がけます。原則誰もが発電事業者や小売電気事業者になれますが、送配電事業だけは、電力小売りの全面自由化後も一般電気事業者である大手の電力会社の送配電部門が行います。一方で、新しく市場に参入した電力会社は一般家庭に供給する電気はあっても、電気を家庭まで送る設備や送配電網を持っていません。新たに自前で電線や電柱を街中に張り巡らせるのも現実的ではありません。そのため、新たな電力会社は手数料を支払って一般送配電事業者の送配電網を利用することになります。その時に支払う送配電網使用料(手数料)が、“託送料金”と言われるものです。言わば電柱のレンタル費用といったものです。
託送料金によっては電気料金が高くなる可能性も
託送料金は、小売電気事業者が電気料金に含めて、各家庭から集めて一般送配電事業者に支払います。託送料金が安ければ、電気料金も安くできるでしょうし、高ければそのまま電気料金に跳ね返ってくるでしょう。この料金は、全国に10ある大手の電力会社が、託送にかかる様々なコストを算出し経済産業大臣に申請、厳正な審査を経た上で認可される仕組みになっています。2015年12月に正式に認可を受け、電力全面自由化から実施される託送料金が決定しました。なお、託送料金には、「低圧」、「高圧」、「特別高圧」の3種類があり、一般家庭や商店向けは低圧料金が、企業や自治体は高圧料金や特別高圧料金が適用されます。2023年度までは、小売事業者を通して発電事業者、送配電事業者へ託送料金が支払 われますが、2024年4月からは、発電事業者も一部の託送料金(発電側課金)を送配電事業者に対して支払う制度が導入されます。これにより、小売電気事業者が支払う金額は減額されるので、託送料金の見直しがなされた際に電気料金への反映が実施されると予想できます。
気になる料金は?
それぞれの電力会社によって送配電設備・施設の状況や、必要なコストが異なるので、電力会社ごとに金額はまちまちです。2024年2月時点で公表されている料金は以下のようになりました(各電力会社の公式サイト等を参考にしています)。
| 北海道電力 | 東北電力 | 東京電力 | 中部電力 | 北陸電力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 272円80銭 (1kW) |
226円60銭 (1kW) |
230円67銭 (1kW) |
214円50銭 (1kW) |
242円00銭 (1kW) |
| 託送単価 | 8円38銭 | 8円58銭 | 7円48銭 | 7円91銭 | 7円39銭 |
| 電気料金 | 11,853円 | 9,652円 | 9,675円 | 9,293円 | 9,515円 |
| 関西電力 | 中国電力 | 四国電力 | 九州電力 | 沖縄電力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 290円40銭 (〜6kW) |
326円70銭 (〜6kW) |
363円00銭 (〜6kW) |
227円38銭 (1kW) |
304円58銭 (1kW) |
| 託送単価 | 7円62銭 | 9円49銭 | 9円38銭 | 8円26銭 | 11円54銭 |
| 電気料金 | 8,264円 | 9,447円 | 9,582円 | 8,418円 | 10,687円 |
※基本料金は一般家庭向けの「電灯標準接続送電サービス」で契約電力を定める場合で、契約電力は1kWあたりの金額です
※託送単価は1kWhあたりの電力量単価です
※電気料金は従量電灯で30Aの契約(関西電力・中国電力・四国電力・沖縄電力は最低料金で計算)、月間の使用量を300kWhとしています(2024年2月現在の金額シミュレーションで口座振替割引額は含みません)
この表を見ると、託送単価が最も安いのは北陸電力の7円48銭、対して最も高いのが沖縄電力の11円54銭となっています。1か月の電気料金が1万円を超えるのは沖縄電力と北海道電力の2県ですが、北海道電力の託送託送単価は8円38銭と、沖縄電力と比べて低くなっています。理由としては、本土との距離が離れているため他の電力会社のように電力会社間で電気を融通しあえないことや、管轄地域に離島が多いことが考えられ、他の地域よりも送配電に関わるコストが高くなっていると思われます。
また、管轄地域に大都市を抱える東京電力、中部電力、関西電力の3社に関しては、7 円48 銭〜7 円91 銭と現状の電気料金(8,264円〜9,675円)に比して、低めに設定された印象があります。なお、現状の電気料金が最も高い北海道電力(300kWhの利用で11,853円)も、8円38銭と電気料金に対してそれほど高くない金額です。
料金設定は基本料金と電力量料金の2本立て。電力量料金単価はシンプルに
託送料金が確定したことで、電気料金の体系が月額固定の“基本料金”と、電力使用量に応じた“電力量料金”の2本立てとなることもわかりました。この仕組みは、電力全面自由化以前の料金体系と同様ですが、家庭用の料金プランとして最も一般的な“従量電灯”では、電力量料金は使用量に応じて3段階の単価が設定されています。例えば、東京電力の場合は、第一段階料金(最初の120kWhまで)は30円00銭(1kWhあたり)、第二段階料金(120kWhをこえ300kWhまで)は36円60銭(同)、第三段階料金(300kWhを超過した部分)は40円69銭(同)と、電気を多く使うほど単価が高くなる料金体系になっています。今回決定した託送料金では、電力量料金が使用量に応じた3段階単価ではなく、使用量に関わらず定額となっているのが特徴です。そのため小売電気事業者は複雑な3段階料金を採用する必要がなくなり、シンプルで自由度の高い料金プランの設定が可能になります。なお、電力全面自由化と同時に従来の“従量電灯”プランが廃止になるわけではありません。2024年2月現在も従量電灯プランは存続していますし、そのほかにも様々な料金プランが登場しているので、自分にあったプランを見つけられると思います。