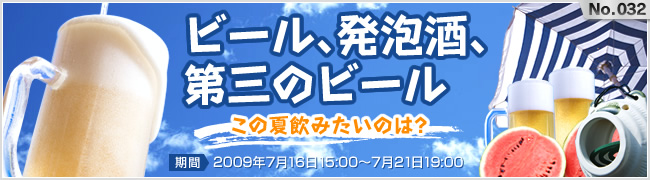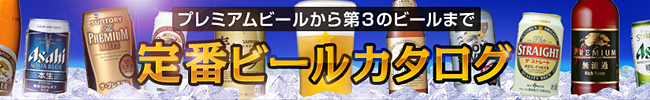今回の価格.comリサーチでは、お酒、とくに「ビール」、「発泡酒」、「第三のビール」に分類されるビール系飲料について調査を行った。ここ数年、「ビール」から「発泡酒」、さらに「第三のビール」へと、価格の安い新ジャンルのビール系飲料へのシフトが起こっている。新聞などの報道機関が伝えるところによれば、今年1〜6月の大手5社によるビール系飲料の課税済み出荷量は、ビール、発泡酒が軒並み前年を下回る中で、価格が安い第三のビールだけが大幅増になっているという。その大きな理由として、昨年秋以降の不景気の影響が考えられるが、一方で、「若者の酒離れ」という現象も影響していると思われる。そんな中、消費者はどんな嗜好性を持って、これらビール系飲料をはじめとするお酒を選んでいるのだろうか。
まず、よく飲むお酒の種類では、世代を問わずビールがトップというやや意外な結果となった。発泡酒や第三のビールが登場した今でも、ビールの人気はさほど衰えていないといえそうだ。ただし、若年層、特に20代の女性の間では、発泡酒や第三のビールよりも、チューハイやカクテル、梅酒などの、ソフトで甘いお酒を好む傾向が顕著となっており、20代男性でも、ビール、発泡酒、第三のビールへの嗜好性は、ほかの年代と比べると著しく低いという結果が出た。若年層の酒離れは如実に表れており、飲まない理由としても「飲めるが、あまり好きではない」という理由が大半を占めた。
逆に年代が高くなればなるほど、日本酒や焼酎、ウイスキーなどの洋酒への嗜好が高まっていく傾向があるが、その一方でビールやビール系飲料についても人気は高く、普段からよく飲まれていることがわかった。お酒を飲む頻度も、全体的に年代が高くなればなるほど、毎日に近い割合に近づいており、お酒全般を好んで飲む傾向が強いということが明らかとなった。
次に、よく飲むビール系飲料の銘柄についてたずねたが、ビールでは「アサヒスーパードライ」やキリン「一番搾り 生ビール」の人気が高い一方で、「ヱビスビール」や「ザ・プレミアム・モルツ」などの高級ビールも一定の人気を得ている。ビールを選ぶ場合、購入時に「味」を重視して購入する割合が圧倒的に多く、ビールを選ぶ際は値段よりも味を重視するという結果になった。
これに対して、発泡酒や第三のビールは、味と同じくらいに価格が重要なファクターとなっており、必ずしも味だけで銘柄を選んでいるわけではない。そんな中、発泡酒では、「淡麗」をはじめとするキリンビールの銘柄が圧倒的に強く、第三のビールでは、各メーカーの銘柄が人気をほぼ等分するという結果になった。価格の安さから人気となっている第三のビールだが、銘柄が多いことに加え、製品サイクルが短いため、消費者のほうでも決まった銘柄やメーカーを選ぶわけではなく、その時々で値段を重視して購入するという傾向が強いものと思われる。
また、全体としてお酒を飲む頻度自体は、昨年と比べてさほど変化はないが、お酒を飲む場所は外食から家へとシフトしてきている。このことからも、昨今の不景気の影響からか、なるべくお金をかけずに飲む頻度は維持しようという意図が見て取れる。なお、年代別に見ると、20代のお酒を飲む頻度は非常に低くなっており、ここからも若年層の酒離れが見えてくる。
以上のことから見えてくるのは、お酒やビールへの嗜好性や飲む頻度自体は全体としてはそれほど変わっていないが、昨今の不況の影響もあり、ビールのほかに発泡酒や第三のビールをチョイスする機会が増えており、飲む場所も、外食から家へと変わってきているということだ。
また、年代別に見ると、若年層の酒離れが確かに進んでおり、ビールには一定の人気があるが、価格の安い発泡酒や第三のビールを選ぶよりも、女性を中心にむしろチューハイやカクテル、梅酒などの、よりソフトなお酒を選ぶ傾向が強い。ビールよりも安いことで人気となった発泡酒や第三のビールであるが、そのメインターゲットは30〜50代であり、実は若年層にはさほどヒットしておらず、逆に同価格帯のソフトなお酒との競合が激しくなっているという状況も見て取れる結果となった。
世代問わず、普段もっともよく飲むのはビール。 若年層にはチューハイやカクテルが人気、年代が高いほど日本酒や焼酎、洋酒にシフト。
普段よく飲むお酒の種類を聞いた。もっとも多かったのは「ビール」で70.3%の割合を占めている。次いで「発泡酒」「第三のビール」が、ほぼ50%程度の割合で2位、3位となった。以上、3種類のビール系飲料は、男性・女性問わずよく飲むと答えた人の割合が大きいが、それ以降の順位となると、男性と女性での嗜好の違いが如実に表れる。
【図1-1、普段飲まれるお酒の種類は次のうちどれですか?
当てはまるものをすべてお選びください。】
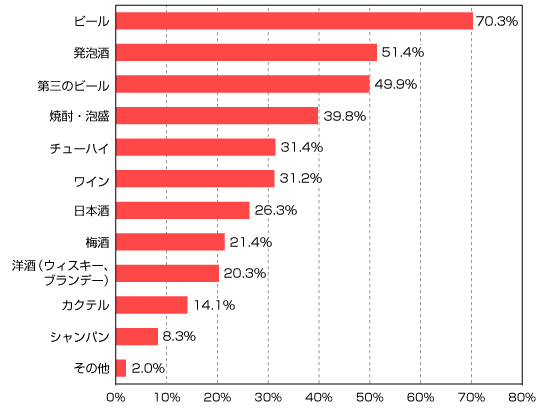
まず男性で多いのは「焼酎・泡盛」で全体の42.2%。次いで「ワイン」(29.7%)、「チューハイ」(29.5%)となり、さらに「日本酒」(27.5%)と続く。これに対して、女性では、「チューハイ」(43.5%)、「ワイン」(41.6%)、「梅酒」(39.1%)、「カクテル」(29.9%)という順位になっており、ビール系飲料以外では、男性と女性で大きく嗜好が分かれた。
【図1-2、普段飲まれるお酒の種類は次のうちどれですか?
当てはまるものをすべてお選びください。(男女別)】
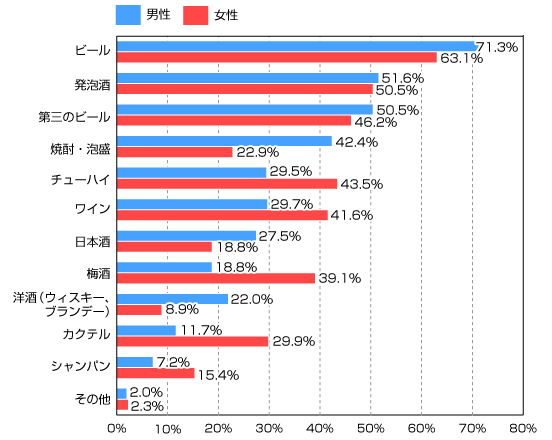
なお、これを年代別に見ると、さらにおもしろい傾向がわかってくる。「ビール」に関しては、どの世代でもまんべんなく好まれる傾向にあるが、20代では「発泡酒」「第三のビール」を好む割合が、ほかの世代に比べて低い。その代わり、20代や30代では、特に女性を中心に「チューハイ」や「カクテル」「梅酒」を好む傾向がほかの世代に比べて高い。発泡酒や第三のビールと、チューハイ、カクテルなどのソフトなお酒は価格的にもほぼ同等であり、同じ価格であれば、ビール系飲料よりもむしろこうしたソフトなお酒を選ぶ傾向が強いといえる。
逆に、50代や60歳以上では、特に男性を中心に「焼酎・泡盛」や「日本酒」「洋酒」を好む傾向が高い。ただしこの年代では、ビールやビール系飲料の人気も同様に高く、お酒全般を好む傾向が強いといえる。
【図1-3、20代が普段飲むお酒の種類】
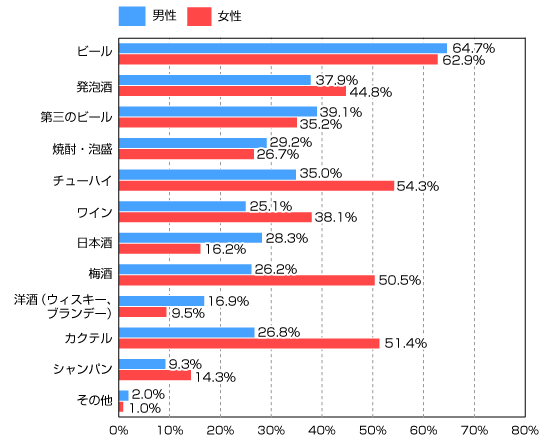
【図1-4、50代が普段飲むお酒の種類】
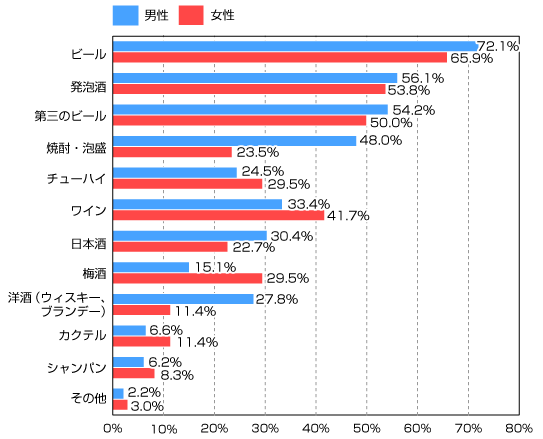
好きなビール1位は「アサヒスーパードライ」、高級志向の銘柄も人気。
発泡酒はキリンの一人勝ち、第三のビールは各社人気を分け合う激戦状態。
ビール、発泡酒、第三のビール、のビール系飲料のジャンル別に、好きな銘柄をうかがった。
まず「ビール」では、「アサヒスーパードライ」が63.3%で一番人気。次いで、キリン「一番搾り 生ビール」(50.1%)、サッポロの「ヱビスビール」(42.9%)という順位となった。1位の「アサヒスーパードライ」と、2位のキリン「一番搾り 生ビール」は、一般的なビール会社のシェアと連動しているが、意外なのは、3位の「ヱビスビール」と、4位につけたサントリーの「ザ・プレミアム・モルツ」(37.5%)だろう。いずれも、一般のビールよりもやや高めな「プレミアムビール」であるが、長らく日本のビールの代表格であった5位の「キリンラガービール」(31.4%)を上回る人気となっており、ビールに関しては、より本格的な味を重視する高級志向に向かっているといえる。
次に「発泡酒」だが、こちらはキリン「麒麟淡麗<生>」が唯一50%を超える55.9%となり、ほぼ一人勝ちの様相を見せた。下位の銘柄を見ても、2位に入った「アサヒ本生ドラフト」(25.1%)を除くと、ベスト5中4つまでがキリンの銘柄で占められており、このジャンルにおけるキリンの存在感の高さをうかがわせる結果となった。
最後に、安さで人気の「第三のビール」であるが、こちらは各社の銘柄が人気を分け合う激戦状態であることがわかる結果となった。一番人気はサントリー「金麦」(40.2%)だが、ベスト5以内に、主要ビールメーカー4社の銘柄がすべて入っており、しかも4位までがそれぞれ30%を超える比較的高い割合を持っている。価格の安さから人気となっている第三のビールだが、銘柄が多いことに加え、製品サイクルが短いため、消費者のほうでも決まった銘柄やメーカーを選ぶわけではなく、その時々で値段を重視して購入するという傾向が強いものと思われる。
【図2、好きな銘柄をすべてお選びください。(複数回答可)】
| 順位 | 銘柄 | 回答数(3,803人中) | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | アサヒビール アサヒスーパードライ | 2,409 | 63.3% |
| 2 | キリンビール 一番絞り 生ビール | 1,907 | 50.1% |
| 3 | サッポロビール ヱビスビール | 1,631 | 42.9% |
| 4 | サントリー ザ・プレミアム・モルツ | 1,425 | 37.5% |
| 5 | キリンビール キリンラガービール | 1,196 | 31.4% |
| 順位 | 銘柄 | 回答数(3,227人中) | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | キリンビール 麒麟淡麗〈生〉 | 1,804 | 55.9% |
| 2 | アサヒビール アサヒ本生ドラフト | 811 | 25.1% |
| 3 | キリンビール 淡麗グリーンラベル | 719 | 22.3% |
| 4 | キリンビール 麒麟ZERO | 456 | 14.1% |
| 5 | キリンビール 円熟 | 441 | 13.7% |
| 順位 | 銘柄 | 回答数(2,963人中) | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | サントリー 金麦 | 1,191 | 40.2% |
| 2 | キリンビール のどごし<生> | 1,032 | 34.8% |
| 3 | アサヒビール クリアアサヒ | 954 | 32.2% |
| 4 | サッポロビール 麦とホップ | 924 | 31.2% |
| 5 | サッポロビール ドラフトワン | 598 | 20.2% |
ビール購入時にもっとも重視するのは「味」
発泡酒・第三のビールは「味」と同じくらい「価格」も重視
ビール、発泡酒、第三のビール、の各ジャンルごとに、購入時にもっとも重視する点をうかがった。
まず「ビール」だが、このジャンルでは圧倒的に「味」を重視する率が高く、その割合は70.7%にものぼった。次点の「のどごし」が16.0%、「価格」が7.7%と大きく開いている点から見ても、ビールを選ぶ人は、何よりもその味にこだわり、価格は二の次という傾向が見て取れる。
これが「発泡酒」になると「価格」の比率がグンと高まり、28.6%にも達する。「味」の割合は36.9%にまで下がり、味と価格とを天秤にかけながら選ぶというパターンが多そうだ。さらに「第三のビール」になると、「価格」(42.1%)が「味」(35.0%)を逆転し、最重要項目となる。実勢価格では、350ml缶が100円ちょっとくらいで売られているケースが多い「第三のビール」だが、その安さゆえ、味よりも安さを重視して買う人が多いという結果になっている。
【図3、ビール、発泡酒、第三のビールを購入する際にもっとも重視する点をお選びください。】
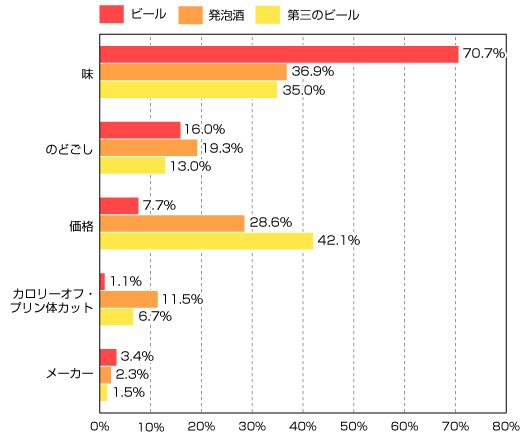
お酒を飲む頻度が高い人ほど「ディスカウントストア」「酒屋」を利用し、「スーパー」「コンビニ」の利用は減少傾向
ビール系飲料・3ジャンルをよく買う場所をうかがった。
全体的には、価格が安く手ごろな「スーパー」で購入するパターンが多く、全体の半数程度を占めている。また、さらに値段が安い「ディスカウントストア」も全体の3割近くにのぼっており、この2つで全体のおよそ8割を占める形だ。そのほかでは、「酒屋」「コンビニ」が約1割ずつ。「インターネット通販」で購入するという割合はわずか数%という結果となった。
この結果を、消費者の「お酒を飲む頻度」の別に見てみると、全体的には、お酒を飲む頻度が高い人ほど、まとめ買いで安く購入できる「ディスカウントストア」と、配達の利便性がある「酒屋」の利用割合が高くなる傾向にあることがわかる。また割合としては小さいものの、「インターネット通販」で購入する割合も増加する傾向にある。逆に、相対的に価格が高めとなる「スーパー」、「コンビニ」の利用割合は、お酒を飲む頻度が高い人ほど減少傾向となっている。お酒を飲む頻度が高い人ほど、「少しでも安いお店でまとめ買い」という傾向が明らかとなった。
【図4、ビール、発泡酒、第三のビールを購入する際にもっとも利用する場所(お酒を飲む頻度別)】
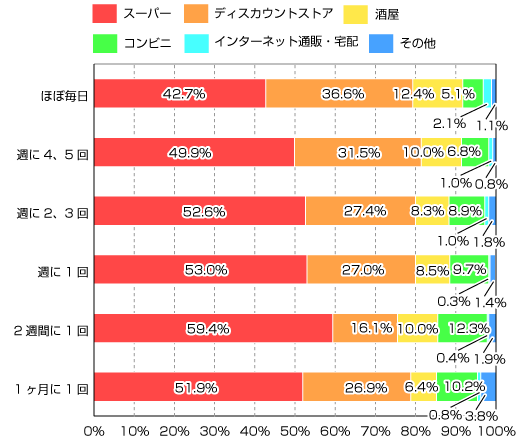
若年層ほど習慣的な飲酒の頻度が低く、お酒を飲まない人の割合も高い
お酒を飲む人を対象に、普段お酒を飲む頻度を聞いた。
もっとも多かったのは「ほぼ毎日」で40.1%。続いて「週に2、3回」(22.2%)、「週に4、5回」(13.9%)、「週に1回」(12.9%)となっており、比較的お酒を飲む頻度は高いことがわかる。
【図5-1、普段お酒を飲む頻度はどのくらいですか?】

これを年代別に見てみると、年代が上がるほど飲酒の頻度が上がることがわかる。60歳以上では「ほぼ毎日飲む」と答えた人が53.4%にのぼるのに対し、20代では14.3%にしか満たない。逆に20代でもっとも多い「週に2、3回」(27.8%)は、60歳以上ではわずか15.4%で、かなり対照的な結果となった。
【図5-2、普段お酒を飲む頻度(世代別)】
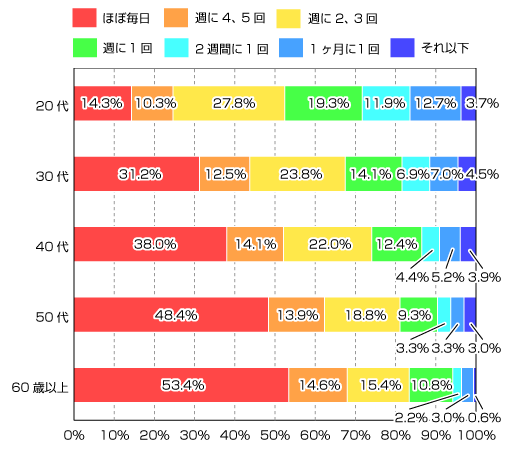
なお、下のグラフは、お酒を飲むか飲まないかを年代別にまとめた結果だが、これを見ても、年代が下がるほど「飲まない」と答える割合が上がっている。若年層ほど、習慣的な飲酒の頻度が低く、またお酒を飲まない割合も高いということが明らかだ。若年層の酒離れが確実に進んでいる結果といえるだろう。
【図6、お酒を飲むか、飲まないか(世代別)】
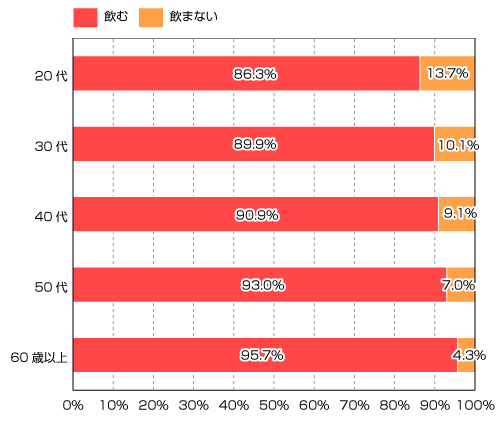
お酒を飲む頻度自体はさほど変わらず。飲む場所は外食から家へシフト
まずは、昨年と比べて、お酒を飲む頻度が変わったかどうかを聞いた。「増えた」「減った」という割合は、それぞれ2割程度ずつあるものの、全体としては「変わらない」と答えた人がもっとも多く、55.2%を占めた。昨年秋以降の不況の影響は、お酒を飲む頻度自体にはさほど影響を与えていないようだ。
【図7-1、昨年と比べて、普段お酒を飲む頻度に変化はありましたか?】
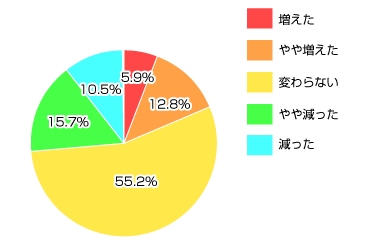
ただし、お酒を飲むシチュエーションの変化を見ると、昨年と比べて増えたものと減ったものが明白になってくる。シチュエーションとして増えたものとしては、「家(自宅または友人宅)」がもっとも多く、全体の46.8%を占めた。「外食」で飲む機会が増えたと答えた人はわずか8.7%で、逆に減ったと答えた人の46.4%を大きく下回る。「アウトドア・イベント」も、増加が2.4%に対し、減少が9.2%となっており、大きく減少していることがわかる。
【図7-2、お酒を飲むシチュエーションのうち、昨年より頻度がもっとも増えたもの】
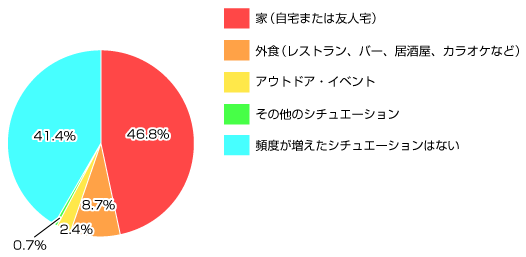
【図7-3、お酒を飲むシチュエーションのうち、昨年より頻度がもっとも減ったもの】
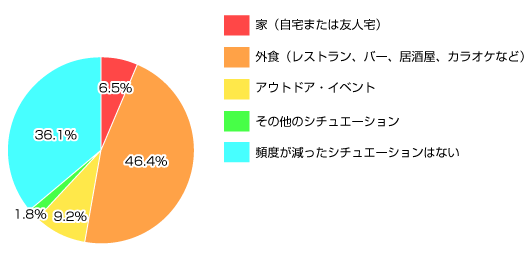
これらの結果から、お酒を飲む頻度自体はほとんど変わっていないものの、お酒を飲む場所としては、家で飲む機会が大幅に増え、外で飲む機会が大幅に減っていることがわかる。お酒自体は飲みたいが、ここ最近の不況の影響もあり、かけられる金額の総額が減っているため、外食を避けて家で飲む、というパターンが広まっているようだ。
若年層の酒離れ傾向が進む。
20代の飲まない理由1位は「お酒は飲めるが好きではない」
「お酒を飲まない」と答えた方に、その理由をうかがった。
年代別に割合の違いはあるが「体質的に飲めない」という方がどの年代でも3割程度おり、「お酒に弱い」という方が2割程度いるため、この両者で全体の約半数を占める。注目したいのは、「お酒は飲めるが好きではない」と答えた人の割合で、若年層になるほどこの割合が高くなっており、特に20代ではその割合が42.9%にものぼる。その上の30代では26.3%でしかないので、いかに20代に顕著な傾向かが見て取れる。
また、年齢が高くなるほど「健康面に配慮して飲まない」という割合が高くなり、50代では17.0%にのぼるが、60歳以上になるとこの割合は5.9%に減少するが、これは「体質的に飲めない」の増加率を考えると、自然なシフトと考えられる。
この結果からも、若年層、特に20代では、「お酒は飲めるが好きではない」という割合が非常に多く、「飲めないのではなく、あまり飲みたくない」という酒離れの傾向が見て取れる。
【図8、お酒を飲まれない方にお聞きします。
お酒を飲まない理由は次のうちどれですか?(世代別)】
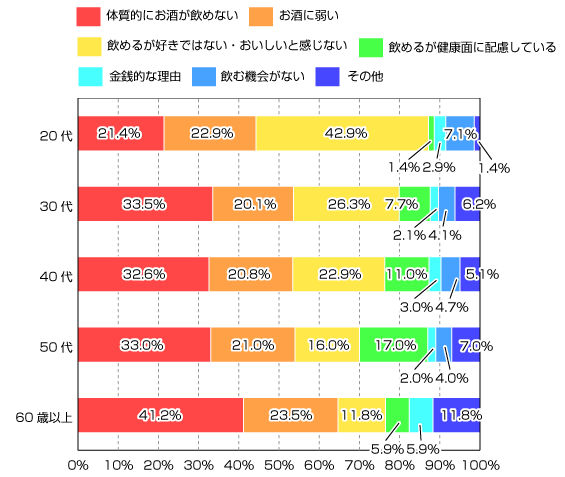
- 調査エリア:
- 全国
- 調査対象:
- 20歳以上の価格.comID 登録ユーザー
- 調査方法:
- 価格.comサイトでのWebアンケート調査
- 回答者数:
- 6,672人
- 男女比率:
- 男87.1%:女12.9%
- 調査期間:
- 2009年7月16日〜2009年7月21日
- 調査実施機関:
- 株式会社カカクコム
※掲載されている金額は検索された結果の参考価格となります。