
サイズが小さくなった「iPad mini」の魅力とCPUがよりパワフルになった第4世代「iPad Retinaディスプレイモデル」の実力をご紹介。新しいiPadはここが違う!
ボディ:とにかく薄くて軽い! 従来の「iPad」とはまったく別物の軽快さ

左が9.7インチ液晶を搭載した「iPad 2」、右が7.9インチ液晶搭載の「iPad mini」。液晶サイズにしてわずか1.8インチの差しかないと思うが、見た目の感じとしては、ベゼル幅などもより狭くなっているため、そのサイズ差以上に小さく感じる。液晶の解像度もまったく同じで、まさに「小さくなったiPad 2」という感じだ
「iPad mini」はよく「小さくなったiPad 2」と称されるが、この言い方はある意味で非常に的を射ている。アップルのサイトでも「ミニなのは、サイズだけ。」というキャッチコピーがついているが、実際「iPad mini」の内部的なスペックは、ほぼ「iPad 2」そのものであり、ディスプレイの解像度なども「iPad 2」とまったく同じため、「iPad miniでできること」は、ほぼ「iPad 2でできること」と同じと考えていいだろう。
ただし、性能は「iPad 2」と同等でも、その本体サイズや重さはまったく違う。採用される液晶サイズが「iPad 2」をはじめとする「iPad」では9.7インチだったのに対し、「iPad mini」の液晶サイズは7.9インチ。わずか1.8インチだけの違いと思うかもしれないが、実際にそのボディを手に取ってみると、このサイズの差は相当大きいことがわかる。
まず、液晶が小型化されたことで、ボディサイズが当然ながら小さくなった。「iPad 2」は、241.2(高さ)×185.7(幅)×8.8(厚さ)mmというサイズだったのに対し、「iPad mini」は、200(高さ)×134.7(幅)×7.2(厚さ)mmというサイズになっている。特に幅については、従来比72.5%ほどに狭まっており、かなり小さくなったという感じを受ける。これは液晶画面を取り巻くベゼルがかなり狭くなっていることが大きい。さらに、8.8mmから7.2mmへと薄くなった厚みも、片手で持ちやすく、携帯性のよさにかなり貢献している。

左が「iPad 2」、右が「iPad mini」。両者の厚みはそれぞれ8.8mm、7.2mmで、1.6mmほど薄くなった。持ってみると、308gというその軽さも手伝って、かなり薄くスリムに感じる
だが、この本体サイズ以上に、「iPad mini」と「iPad 2」の違いをハッキリと認識できるのは、その重量かもしれない。「iPad 2」(Wi-Fiモデル)は重量が601gあったのに対し、「iPad mini」(Wi-Fiモデル)の重量はわずか308g。ほぼ半分の重さしかないのだ。ボディサイズは「iPad 2」の7〜8割の面積ダウンでしかないのに、重さは半分になっているというのはかなりのインパクトであろう。実際に「iPad mini」を手にしてみるとわかるのだが、とにかく「軽い」のである。従来の9.7インチ液晶の「iPad」はやや重く、片手で長時間持つという使い方は正直厳しかった。両手でしっかり持つか、あるいは机などに置きながら使うというのが一般的な使い方だったかと思うが、今回登場した「iPad mini」なら、片手でひょいと持って使える。この手軽さが、「iPad mini」の最大の特徴であり、最大の魅力なのだ。

重量が308gと、従来の9.7インチ「iPad」の約半分しかないので、片手でも楽々持って利用できる。あまりにも手軽なので、思わずどこへでも持って行きたくなる。これが「iPad mini」の最大の魅力だ
液晶画面:解像度は「iPad 2」とまったく同じ。液晶自体は明るく鮮やか

画面サイズは異なるが、解像度は従来の「iPad 2」とまったく同じ。当然ながら、画面に一度に表示できる情報量も同じとなる。こういうところも「iPad mini」が「小さくなったiPad 2」と呼ばれるゆえんだ。もちろん、アプリなどもそのままの解像度で問題なく動作する
すでに説明したように、「iPad mini」は「iPad 2」の小型版と考えるとわかりやすい。液晶サイズは9.7インチから7.9インチにコンパクト化されているが、解像度はまったく同じ1024×768ドットで、一画面に表示できる情報量もまったく同じだ。このため、これまでの「iPad 2」で行えていたことは、「iPad mini」でも問題なく行える。解像度がまったく同じなので、アプリなどの表示もスケーリングを使わずにそのまま行われる。これは、過去のアプリ資産をそのまま生かせるという意味では、大きなポイントだろう。第3世代以降の「iPad」で採用されるようになった「Retinaディスプレイ」を採用しなかったことを悔やむ声も一部では聞かれるが、「Retinaディスプレイ」は重量や消費電力の点で不利になるのと、同じ解像度のディスプレイのため「iPad 2」の資産をそのまま生かせるメリットのほうが大きいと考えたほうがいいかもしれない。

上が「iPad 2」で、下が「iPad mini」。同じ明るさ設定(中間輝度設定)での撮影となる。全体的に見て、「iPad mini」の画面のほうが明るいことがひと目でわかる。白い雲の部分などを見るとわかるが、色味は「iPad 2」のほうがやや青みがかっているのに対し、「iPad mini」のほうは白の色純度が高く、肉眼で見たのに近い自然な色合いになっている
(※「iPad 2」のほうは、表面に保護フィルターがかかっています)
このように、「iPad mini」の液晶画面は「iPad 2」と解像度がまったく変わらず、「Retinaディスプレイ」も採用されなかったことから、あまり見るべきものはないと思っている人もいるかもしれないが、それは違う。「iPad 2」の発売から1年半が経過して登場した「iPad mini」だけに、液晶パネル自体のレベルは間違いなく上がっている。2台を比べて見るとすぐにわかるが、「iPad mini」の液晶は、「iPad 2」の液晶よりも基本的に明るく見やすい。画面がひと回り小さくなったことで、エッジ型バックライトの明るさが効率よく拡散しているということもあるのだろうが、基本的な液晶パネルの輝度が高いように感じる。また、色味的にも、従来の「iPad 2」がやや青みがかっていたのに対し、「iPad mini」の液晶はより白純度が高くなった感じを受ける。そのため、写真などの色の鮮やかさが、「iPad mini」のほうがキレイに感じられるのだ。このように、「iPad mini」の液晶画面は、「iPad 2」に比べても一段高いレベルの画質を実現しているといえる。
なお、タッチパネルのタッチ感だが、これは両者でかなり異なっている。「iPad 2」など9.6インチiPadでは、硬質なガラスが画面表面に使われているため、タッチした感触も硬いが、「iPad mini」では、表面がガラスではなく樹脂になっているため、やややわらかく、タッチした感触も少しやわらかい。このあたり好き嫌いはあるだろうが、ガラスを採用しないことで重量を軽くできた半面、強度面がやや犠牲になっているところかもしれない。
処理速度:処理速度はこれまでの「iPad」シリーズとほぼ同等。必要十分な速度
「iPad mini」と「iPad 2」では、タブレットの頭脳であるCPUに、同じ「デュアルコアA5チップ」を採用している。このあたりのスペックが同一なのも、「iPad mini」が、「小さくなったiPad 2」と称される大きな理由だ。同じCPUを採用しているので、処理速度に関しても、ほぼ「iPad 2」と同等と思われるが、実際のところはどうなのだろうか。ベンチマークアプリ「Geekbench 2」を使って、簡単なベンチマークテストを行ってみた。
- iPad 2

- iPad mini

ベンチマークテストアプリ「Geekbench 2」のスコア。左が「iPad 2」で、右が「iPad mini」となる。スコア上は「iPad 2」のほうが11ポイントほど高いが、搭載するCPUが同じと言うこともあり、ほぼ同程度の性能と言っていいだろう
結果は上のテスト結果画面の通りで、「iPad mini」のトータルスコアが「752」なのに対し、「iPad 2」のトータルスコアが「763」という結果となった。若干のスコア差はあるが、これを見る限り、「iPad mini」と「iPad 2」は、ほぼ同程度の性能と言って差し支えない。ちなみに、初代「iPad」のトータルスコアは「471」という結果だったので、初代よりは間違いなく高速だ。また、「Retinaディスプレイ」を採用した第3世代の「iPad」のトータルスコアも「755」だったので、「iPad mini」とほとんど変わらない。さすがに、「iPad mini」と同時に発表された最新の「iPad」(第4世代)は、最新鋭の「クアッドコアグラフィックス搭載デュアルコアA6Xチップ」を搭載しているので、トータルスコアも「1775」とぶっちりぎりのスコアを叩き出しているが、それ以外の「iPad」と比較しても、「iPad mini」の処理性能が遅いと言うことはない。むしろ、小型になったのに、処理速度が落ちていないことは、特筆すべきポイントだろう。
実際の使用感でも、「iPad mini」の操作感は悪くない。さすがに、一世代前のデュアルコアCPUだけにすごく速いというわけではないが、一般的なWebブラウジングなどであれば、必要十分な処理速度だ。これまでの「iPad」を使っていた人であれば、さほど違和感は感じないだろう。「YouTube」などの動画コンテンツも問題なく表示できており、不満を感じる点は少ないといえる。
カメラ:最新の第4世代「iPad」と同じ5メガピクセルの高精細カメラを搭載

背面左上に搭載されるメインカメラは500万画素クラスの高精細カメラ。裏面照射CMOSセンサーを採用しており、暗い場所での高感度撮影にも強い。この点は、同時に発売された「第4世代iPad」とも共通するスペックとなっている
これまで見てきたように、「iPad mini」は「iPad 2」とほぼ同等のスペックを備えた「小さくなったiPad 2」なのだが、唯一大きく異なっている点がある。それは「カメラ」の機能だ。「iPad 2」では、裏面のメインカメラが70万画素相当のカメラだったのに対し、「iPad mini」のメインカメラは500万画素相当のカメラにスペックアップしている。動画に関しては1080pのハイビジョン撮影が可能だ。また、液晶画面の上にあるフロントカメラ(FaceTimeカメラ)も、「iPad 2」ではVGA画質(640×480ドット)の30万画素程度だったものが、「iPad mini」では120万ピクセル程度までスペックアップしており、撮影できる映像も720pにまで対応するようになった。実は、このカメラは、最新の第4世代「iPad」とまったく同じスペックとなっており、カメラに関して言えば、「iPad mini」は最新モデルと遜色ないスペックを実現している。
実際にこのカメラでいくつかのサンプル写真を撮影してみたが、「iPad 2」に比べるとさすがに画素数が大幅にアップしていることもあって、写真の1枚1枚が非常に鮮明だ。オートフォーカスの合焦時間も短く、ホワイトバランスも適正に設定されるので、撮影した写真の画質は、やや明るめに調整される傾向はあるものの悪くはない。実は、同じアップルの「iPhone」シリーズでも、ここ数年のうちに発売された「iPhone 4」「iPhone 4S」「iPhone 5」は、代を追うごとにカメラの画質がよくなっていっているのだが、この「iPad」でも同じことが言える。カメラに関しては、着実な進化を遂げていると言っていい。
- iPad 2

- iPad mini

左が「iPad 2」で撮影した写真で、右が「iPad mini」で撮影した写真。同じ場所から撮影したのだが、画角がまったく異なるため、「iPad 2」ではイチョウの木がフレームに収まらなかった。その点500万画素の「iPad mini」のカメラでは、広角で撮影でき、解像度も高く、細かいイチョウの葉の色味などもしっかり描写できている
- iPad 2

- iPad mini

左が「iPad 2」で撮影した写真で、右が「iPad mini」で撮影した写真。やはり画角自体が異なっているため、同じ場所からでも撮影できる幅が異なっている。これは室内の白熱灯下での撮影サンプルだが、左の「iPad 2」はやや暗く、色味も悪い。右の「iPad mini」のほうが全体に明るく、ホワイトバランスも適正で、解像感も高い
バッテリー性能:バッテリー自体の容量は小さくなったが、駆動時間は10時間を確保

ボディが小型化したのにともない、バッテリー容量自体も小さくなっているが、それでもバッテリー駆動時間は10時間を確保している。なお、充電は付属のUSBケーブルでパソコンから給電する方法と、コンセントに差し込むためのアダプターを介した直接充電の2通りが選べる
「iPad mini」の美点は、そのバッテリー性能にもある。一般的には、本体が小型化すると、それだけ搭載できるバッテリー容量も小さくなってしまうので、同じ性能であれば、バッテリー持続時間は減るのが普通だ。しかしながら、「iPad mini」においては、カタログスペックで「Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生:最大10時間」とうたっており、「iPad 2」と基本的には変わらないバッテリー性能を実現しているのだ。これは驚くべきポイントである。
スペックを細かく見ていくと、「iPad 2」では、25Whのリチャージャブルリチウムポリマーバッテリーを採用していたが、「iPad mini」では、16.3Whのリチャージャブルリチウムポリマーバッテリーとなっており、バッテリー容量だけで見ると、本体サイズの小型化の影響で、65%程度にまで減っている。それでありながら、同じだけのバッテリー持続時間を維持できているのは、ひとえに内部の省電力設計のたまものであろう。搭載するCPUは変わっていないので、このバッテリー消費に大きく影響しているのは、やはり液晶パネルの性能と思われる。上でも見たように、液晶パネル自体の見た目の明るさはむしろアップしているのに、消費電力は抑えられているのだ。

「iPhone 5」から採用された8ピンの「Lightningコネクタ」を採用。従来の20ピン「Dockコネクタ」用の周辺機器はそのままでは利用できない。その代わり、本体下部のレイアウトに余裕ができたおかげで、ステレオスピーカーが搭載されている
なお、本体の充電やパソコンなどの機器との接続に使われるコネクターは、従来の30ピン「Dockコネクタ」から、新しい8ピンの「Lightningコネクタ」に変更されている。「Lightningコネクタ」に関しては、この秋登場した「iPhone 5」でも採用されているもので、従来の周辺機器がそのまま使えなくなる(別売の変換コネクタで接続可能)などの問題はあるが、コネクター自体が小型化されたことは、長期的に見ればメリットが大きい。「iPad mini」でも、本体下部のコネクターが小型化された分、レイアウト的に余裕が生まれ、コネクターの左右にスピーカー口が設けられているが、これは内部的にもステレオスピーカーになっているということで、従来のモノラルスピーカーだった「iPad」からの進化のひとつと言えるだろう。なお、同梱されるACアダプターも小型のものに一新されている。
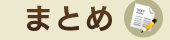 性能は「iPad 2」と同等だが、その小ささ・軽さはまるで別物
性能は「iPad 2」と同等だが、その小ささ・軽さはまるで別物以上、「iPad」ファミリーに新しく加わった7.9インチ液晶搭載の「iPad mini」の性能に関して詳しく見てきた。冒頭に述べたように、「小さくなった『iPad 2』」と称される「iPad mini」であるが、その内容を見ると、「単に小さくなった」というよりも、「よくここまで小さくできたな」という驚きの連続であることがわかる。むしろ、これだけボディを小型・軽量化しながら、9.7インチの「iPad 2」と同等以上の性能を実現できたことに賞賛を送りたいほどだ。
特に、そのボディの薄さ・軽さは、これまでの「iPad」シリーズとはまったく異なる製品と言ってもいいほどに際立っている。従来の「iPad」に対しては、その便利さは理解しながらも、ボディの大きさ・重さから購入に至らなかったという方も実は結構いるのではないかと思うが、この「iPad mini」であれば、問題ない。これまでは大変だった、通勤電車の中での片手持ち利用も十分に現実的だし、そうなれば利用シーンも一気に広がる。サイズ的にもちょっとした単行本サイズなので手ごろだし、バッグなどにもスッと入れておきやすい。特に、女性ユーザーには歓迎されるだろう。そういう意味では、これまでの「iPad」以上に「使える」タブレットに仕上がっている製品といえる。
![]()






