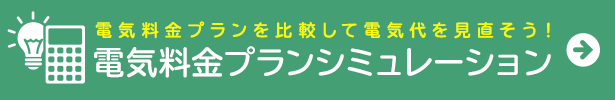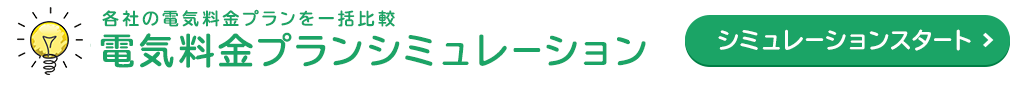電力自由化
更新日:2024年04月17日
2020年に実施された“発送電分離”ってなに?

電力自由化とは、“発電”、“電力小売”、“送配電”の3つが自由化されること
「電力自由化」とは、“発電”の自由化、“電力小売”の自由化、“送配電”の自由化のことを言います。
発電の自由化とは、従来から地域にある10の大手電力会社(一般電気事業者)や新電力・PPSと呼ばれていた特定規模電気事業者だけでなく、誰もが発電事業者として電力会社になれることで、電力小売りの自由化とは、誰もが小売電気事業者として電気を一般消費者に販売できることを言います。
2016年4月からは、3つの自由化のうち“発電”と“電力小売”の自由化が本格的に始まりました。
一般家庭ではこれまで東京電力や関西電力といった、自分が住んでいる地域の電力会社としか契約できませんでした。しかし、自由化された現在はどの電力会社からでも自由に電気を購入することが可能です。発電をしたり、電力小売りをしたりする電力会社が増えたことで、電力会社間の競争は高まっています。消費者にとっては、電気料金の値下げ、新たな料金プランの登場、従来にないサービスの提供が大いに期待できます。
“発送電分離”の必要性
発電所で作られた電気は送配電設備や送配電網(送配電ネットワーク)を通じて、工場や大型施設、一般家庭といった需用家、つまり消費者に届けられます。こうした設備や送配電網は、発電設備とともに東京電力や関西電力などの大手電力会社が所有しています。2016年4月の電力小売の全面自由化後は、それぞれの電力会社の“送配電部門”が移行した一般送配電事業者が送配電を行いますが、実質的にはこれら大手の電力会社が引き続き行っているのと変わりません。
一方で、新しく市場に参入した電力会社には一般家庭に供給する電気はあっても、電気を利用者に届ける設備や送配電網がありません。新たに自前で電線や電柱を街中に張り巡らせることは、コスト面や景観、限られた空間や土地を利用することを考えても現実的ではありません。そのため、新たな電力会社は手数料を支払って一般送配電事業者の送配電網を利用することになります。発電を行い送配電網も持つ大手の電力会社、大手・中小を含めて新規参入した電力会社、こうしたすべての電力会社が同じ土壌で公正な競争を行うには、共通のインフラである送配電網をすべての電力会社が公平かつ自由に利用できなければなりません。
送配電を行う会社が、ライバル電力会社の手数料だけを高くするとか、送配電網を利用させないというようなことはあってはなりませんし、そうした可能性も排除しておく必要があります。こうして、公正な競争を促すための新たな仕組み作りとして導入されたのが、大手電力会社の発電部門と送配電部門を分ける“発送電分離”なのです。“発送電分離”を行うことで、どの電力会社がどこへでも送配電網を使って電気を送れる“送配電”の自由化を実現することができ、しっかりとした競争的環境を整えることができるわけです。
そんな重要な “発送電分離”が2016年4月に実施されなかった理由は?
2016年4月の電力小売りの全面自由化では、“発電”と“電力小売”の自由化は行われましたが、“送配電”の自由化は行われず、送配電の自由化(発送電分離)は2020年4月からスタートしています。公正な競争のために必要と言われる“発送電分離”が2016年4月に行われなかった理由はなんでしょう?
2016年4月から、各地域にある電力会社は、発電・小売・送配電を行う3つの事業部門に分かれてそれぞれ事業を行っています。2020年4月からは、送配電を行う事業部門(一般送配電事業者)は法的に分離され、別会社とすることが義務付けられました。今まで1つの会社内でやっていたことを分離するので、労使関係の調整や資産の仕分け作業、さらには連絡体制の構築などやるべきことはたくさんあります。こうした準備には相当の期間がかかることや、混乱を避けて慎重に進めていきたいといった実情がありました。また、税法上の措置の検討や、新たな設備投資に対する資金調達といったことへの配慮も必要です。大胆な改革だけに、段階ごとに課題や問題点を洗い出して評価・チェック、さらには海外の先行事例なども検証しながら現実的なスケジュールで実行していく必要があったのです。
電力会社の多くが分社化をスタートする一方で例外も
2020年4月に実施となった“発送電分離”ですが、電力会社によってその取組みには温度差が見られました。たとえば、東京電力では、“燃料・火力発電部門”、“送配電部門”、“小売部門”の3つの部門を2016年4月に分社化。持株会社である東京電力ホールディングスの傘下に入り、いち早く“発送電分離”をスタートしています。そのほか各電力会社においても、発送電分離を補完する仕組みやルールを慎重に整備したうえで分社化に至っています。
一方で、沖縄電力は一般送配電事業者の兼業認可申請を行い、兼業規制の例外として認可されました。これは、「一般送配電事業者が発電・小売事業を営むことが区域内の電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合には、経済産業大臣の認可を得た上で、法的分離を行わなくてもいいこととされている。」という規定に基づくもので、沖縄地域では災害対応などに3部門が一体となって活動する必要性が特に高いといった実態を踏まえて考慮されたためです。ただし、各電力会社と同様に、自社の発電・小売電気事業を有利にするような行為の禁止などの規制は適用されます。
“発送電分離”によって電気の安定供給の責任は送配電事業者へ
電気は社会生活や経済活動に欠かせない存在です。電気は、「同時同量」と言って、常に需要と供給を一定の範囲内で一致させる必要があります。これまでは、一般電気事業者が管轄エリアの需要量に合わせて、発電所の運転を綿密にコントロールして発電量を調整し、同時にピーク需要の8〜10%程度(供給予備率)の余裕がある発電量を確保、自然災害や設備の故障などのトラブルが起こっても対応できるように余力をもって臨んでいました。
また、電気を供給するという義務(供給義務)も負っていましたが、“発送電分離”後は東京電力や関西電力などの一般電気事業者に課されていた供給義務は撤廃されます。その後は、一般送配電事業者が送配電設備や送配電網を運用し需要と供給のバランスを厳密に管理、電力の品質を維持する義務を担います。一般送配電事業者がしっかりと需給バランスを調整するには、発電事業者間のルール作りや、電気を自由に調達できる市場の創設など、緻密な仕組み作りも求められています。