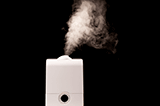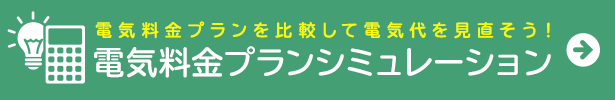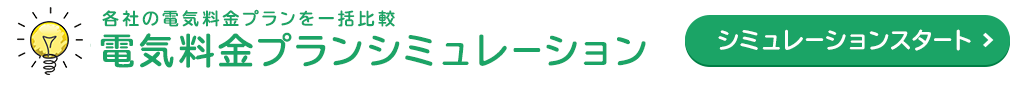更新日:2024年04月17日
蛍光灯はつけっ放しが電気代はお得?消費電力量が多い照明器具を節電!

家庭内で消費電力量が3番目に多いのが照明器具ってご存知でした?
家庭内には多種多様な電気機器がありますが、機器別で消費電力量の多い順番はご存知でしょうか?全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)が公表している「令和3年度家庭部門のCO2排出実態調査事業委託業務(令和3年度調査分の実施等)報告書 世帯当たり年間消費量の機器別構成(2019年度)」によれば、家庭内で最も電力を消費しているのはエアコンで全体の14.7%、2番目は電気冷蔵庫で14.3%、続いて照明器具が13.5%、テレビ(9.4%)、パソコン(3.9%)、ビデオレコーダー(2.4%)となっています。これら上位6つの機器で、家庭内の約半分の電力を消費していることになります。また、電気機器の種類が少なくなるオフィスでは、照明器具が消費する電力は全体の3割程度と言われています(一般社団法人日本照明工業会より)。割合の多くを占める照明器具の節電が進めば、その分支払う電気代が安くなるわけです。
ところで、蛍光灯はこまめに消すのが良いのか、つけっぱなしが良いのか?
「蛍光灯などの照明器具は短時間であれば、消さずにつけっぱなしのほうが電気代が安い」という話をお聞きになったことはありませんか? これは、照明器具は点灯する瞬間に多くの電力を消費するので、こまめにオン・オフを繰り返すとかえって電気代が高くなると言われているためです。点灯する瞬間に電力を最も消費するのは間違いないのですが、長い時間点灯している時ほどの電力を消費することはありません。理論上は数分といった短時間ならつけっぱなしのほうが節電になるのでしょうが、基本的には人がいない時など、必要のない場合はこまめに照明器具のスイッチをオフにする姿勢で臨むほうが節電につながります。
ただし、短時間にひんぱんに点灯と消灯を繰り返すと照明器具自体の寿命が短くなるということがあります。東芝ライテックのQ&Aによれば、「比較的短時間の点滅を繰り返した場合は、器具のタイプや環境にもよりますが1回あたりに約1時間程度短縮されます」と書かれています。こうなると、「何分ならつけっぱなしのほうがいいの?」ということが気になりますが、これを求めるのは、使っている蛍光灯の違いや、点灯時間と消灯回数など非常に複雑な条件設定が必要となり単純な結論には結びつきません。同じく、東芝ライテックのQ&Aに、“数分間隔でのON/OFFはかえって不経済ということになりかねません。数十分以上の間隔であれば問題ないと思われます”ともあるので、こちらを参考にされてはいかがでしょう。
蛍光灯式シーリングライトの電気代はいくらかかるの?
それでは、具体的な照明器具の電気代をチェックしてみましょう。実は、天井などに設置するシーリングライトのほとんどはLED式に替わっていて、各社のカタログから蛍光灯式のシーリングライトはほとんどはずれてしまっています。機器別の詳細な消費電力はわかりませんが、8〜10畳用の家庭用蛍光灯式シーリングライトの消費電力は70〜80W程度です。ここでは、75Wとして計算してみましょう。
75W÷1000×29円(1kWh当たりの電気代)=2.175円 これが、1時間当たりの電気代です。1日では52.2円、1年では19,053円となります。1年間つけっぱなしということはないでしょうが、朝出かける時に消し忘れたなんて場合は、10時間程度は無駄な電力を消費していることになり、21.75円の電気代を損していることになります。もちろん、照明器具はシーリングライトだけではありません。トイレや洗面所、玄関など家の中にはたくさんの照明器具があります。やはり、人がいない時や出かける時など、必要のない照明器具はこまめに消すことが大切ですね。
蛍光灯式をLED式に替えたら電気代は安くなる?
近年は各社から発売される照明器具のほとんどがLED式になっています。資源エネルギー庁の「省エネ性能カタログ2023年版」を参考にすると、8畳用の家庭用LEDシーリングライトの消費電力は平均で30Wでした。
30W÷1000×29円(1kWh当たりの電気代)=0.87円
これが、1時間当たりの電気代です。1日では20.88円、1年では7,621.2円となります。蛍光灯式と比べると電気代はずいぶん安くなります。一昔前は、LED式の照明器具自体の価格が高いため、電気代が安くなることはわかっていてもあまり普及が進みませんでした。しかし、今では価格も下がり、節電意識の高まりもあって自宅の照明器具をLED式に変更している方が増えています。
蛍光灯とLEDについてのまとめ
最後に蛍光灯とLEDの特徴について整理しておきましょう。
価格
かつてはLED式の照明器具は価格が高く、蛍光灯式の何倍もしましたが、現在はかなり下がっています。さらに、機能を調光や調色といった基本機能(調光・調色機能については下記を参考にしてください)にしぼることで低価格で販売されている機種もあり、必ずしも“LED式=高価”とは言えなくなってきました。
省エネ性能
LEDは多くが発光に使われる(発光効率が高い)ため、省エネ性能が高く節電につながります。また、熱となって失われる電気も少ないので発熱も抑えられます。
寿命
一般的な蛍光灯の寿命は6,000〜1万3,000時間、長寿命のタイプでは2万時間以上あります。一方でLEDは4万時間とされています。ただし、蛍光灯式は蛍光灯自体を交換できますが、電球式のLEDは別にして、シーリングライトのようにLEDが内蔵されている場合はLEDだけの交換ができないので、器具ごと交換します。
光の成分
蛍光灯には赤外線や紫外線が少し含まれています。一方で、LEDの発光成分には、赤外線や紫外線がほとんど含まれません。そのためLEDでは紫外線を好む虫が寄り付きにくい、紫外線による展示物の劣化を防げる、といった効果も期待できます。
調光機能
照明の明るさを変えられる機能が調光機能。LED式ではほとんどの照明器具に備わった機能ですが、古いタイプの蛍光灯式では調光機能がないものもあります。
調色機能
赤味がかった白熱電球の色から白く青みがかった色合いまで、明かりの色を変化できる機能です。蛍光灯式では、昼白色、昼光色、電球色の中から好みの色合いを選びますが、調色機能があるLED式の場合は自由に好みの色合いに変化させられます。
なお、新聞やテレビなどで「白熱灯(白熱電球)、蛍光灯(蛍光ランプ)が2020年をめどに実質製造禁止となる」という報道がありました。一般社団法人日本照明工業会のWebサイトには、この件について経済産業省に確認した内容の説明があります。それを引用すると、「エネルギー消費効率の高い製品の普及促進をめざし、製造事業者等に機器等のエネルギー消費効率の向上努力を求めているトップランナー制度に関して、照明製品を一本化した新たなトップランナー制度の導入検討がこれから開始されますが、これは2020 年に白熱灯(白熱電球)、蛍光灯(蛍光ランプ)の製造を禁止するものではないとのご回答をいただきました」ました」とあります。省エネ化の推進にともないLEDの普及が広まっているなか、白熱灯は国内の主要メーカーでは生産終了となっているところがほとんどです。蛍光灯については「水銀に関する水俣条約」において、直管蛍光灯の製造と輸出入を2027年末までに禁止することで合意されました。また、電球形蛍光灯はすでに2025年末での製造・輸出入禁止が決まっているため、すべての一般照明用蛍光灯の製造が終了する見込みです(2024年1月現在)。
電気代を節約したい!電気料金プラン比較
蛍光灯からLEDに変更するのはもちろん電気代を節約するのに役立ちます。しかしながら、今使える蛍光灯を捨てにくかったり、LEDライトを買うのに初期費用がかかります。そんな時にはまずは電気料金プランを見直すことから始めてみましょう。価格.comのシミュレーションでは、お住まいの地域でどんなプランが提供されていて、どのプランに切り替えるといくら節約となるかが一目瞭然です。さらに、おトクなキャンペーンも随時行われていますので、プランの切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。