2025年7月7日 更新
経費精算システムの導入を検討する中小企業にとって、コストと機能のバランスは非常に重要です。本記事では、初期費用ゼロや月額料金が抑えられたサービス、従量課金制やユーザー数に応じた柔軟な料金体系を採用している製品など、コストパフォーマンスにすぐれた14の経費精算システムを厳選。操作性や連携機能にも配慮しつつ、「導入しやすく、長く使いやすい」ツールを4タイプに分けて紹介します。コスト重視の方に必見です。
- この記事を監修した専門家
- 執筆・監修 伴洋太郎さん

- BANZAI税理士事務所 代表
税理士、1級ファイナンシャルプランニング技能士
大学卒業後、一般企業や税理士事務所での勤務を経て税理士試験に合格し、2018年にBANZAI税理士事務所を開業。個人事業主や中小法人を対象とした業務の経験が豊富で、業務のデジタル化支援や個人事業の法人化等に数多く携わる。 著書「7日でマスター フリーランス・個人事業主の確定申告がおもしろいくらいわかる本」(ソーテック社)
この記事で紹介している経費精算システムはこんな中小企業におすすめ
- 少人数の体制で経費精算の効率化に取り組みたい企業
- 初期費用をかけず、まずはスモールスタートしたい企業
- コストと業務改善のバランスを重視し、最も費用対効果の高い選択をしたい企業
中小企業に向いている経費精算システムのおすすめ4タイプ
1.従量課金制で柔軟な料金プランを提供
こんな企業におすすめ
- 月額固定費よりも、利用状況に応じた費用発生を望む企業
- 成長フェーズにあり、人員の増加や利用部門の追加を見越している企業
- 月ごとの経費精算の件数や対象者数にばらつきがある企業
このタイプのメリット・デメリット
- メリット
- ユーザー数や申請数などに応じた課金で、むだなコストを抑えやすい
- コストに応じて機能を拡張できる柔軟性がある
- 小規模から段階的に導入でき、試験導入にも向いている
- デメリット
- 利用量が急増すると、結果的に定額のプランより高額になることもある
- 機能追加や利用拡大にともなって想定外の出費になることがある
- 利用状況を正確に把握・管理しないとコスト予測が難しくなる
導入前に担当者が検討するべきこと

- サービスごとの従量課金の基準(件数・人数・機能など)を把握しておく
- 社内の月間の申請件数やユーザー数が今後どの程度増減しうるかを見積もる
- 利用拡大時の料金シミュレーションを行い、コスト上限や他サービスへの移行可能性を事前に検討する
専門家からの選び方アドバイス
従量課金タイプのシステムは、少人数から導入できる柔軟性や費用対効果の高さが魅力です。しかし、利用が拡大するにつれ、想定以上にコストが膨らむリスクもあります。課金基準を細かく確認し、自社の利用パターンをもとに将来の費用推移をシミュレーションしておくことが重要です。必要であれば、あらかじめ移行可能な代替サービスも視野に入れ、長期的な運用設計を検討しましょう。
従量課金制で柔軟な料金プランを提供する経費精算システム一覧
-
この製品の特徴サマリ
- 50名以下の法人向けに3プランを用意。基本料金は年額32,736円(ひとり法人プラン)からで、企業規模に応じて選択できます
- 「ビジネスプラン」ではアクティブユーザーが6名以上から1名あたり550円/月の従量課金制を採用。むだなコストが発生しない柔軟な料金体系となっています
- 初期費用無料で、最低利用期間の縛りによる解約費用あんども発生しません。中小企業が気軽に導入できる、負担の少ないコスト設計を実現しています
50名以下の法人向けプランは、企業の規模に応じた3つを用意。契約プランごとに利用できる人数は変動し、「ひとり法人プラン」は1名まで、「スモールビジネスプラン」は3名まで利用可能。「ビジネスプラン」では基本料金だけで5名まで利用でき、それ以上は従量課金となります。従量課金の対象はアクティブユーザーとなっており、アカウントを持っていても利用がなかったユーザーは課金対象外(管理権限・承認権限付与者は除く)。柔軟な料金体系によってむだなコストを抑えられます。最低利用期間の縛りや解約費用がないのも特徴です。
価格.com編集部が実際に使ってみた使い方・使用感レポートを掲載中
マネーフォワード クラウド経費について詳しく見る -
この製品の特徴サマリ
- 基本料金+経費精算を作成した「アクティブユーザー」1人あたり330円が月額料金となる従量課金型のシステム
- 領収書のデータ化件数がアクティブユーザー×30件を超えると追加料金として、超過30件につき330円が加算されます
- 必要機能に応じてミニマム・ベーシック・プロフェッショナルの3プランから選択でき、基本料金はプランに応じて決まります
基本料金(2,178円〜)+アクティブユーザー1人あたり330円が月額料金となる従量課金型のシステムです。経費精算を作成したユーザーをアクティブユーザーとし、数は月ごとにカウントされます。また、領収書のデータ化件数がアクティブユーザー×30件を超えると超過30件につき330円が追加料金として発生します。搭載機能の異なるミニマム・ベーシック・プロフェッショナルの3プランが用意され、プランに応じて基本料金が決まります。会社の規模やシステム利用状況に応じた料金で利用できるため、中小企業でも導入しやすくなっています。
価格.com編集部が実際に使ってみた使い方・使用感レポートを掲載中
invox経費精算について詳しく見る -
この製品の特徴サマリ
- 利用料金は、初期費用と経費精算の処理件数に応じた年額費用で構成。ユーザーごとに最適な利用料金が設定されます
- 専任担当者による導入・運用支援が付帯し、定着までサポートを受けられるため、システム導入に不慣れな企業でも安心して利用開始できます
- Bill Oneビジネスカードと一体となった経費精算システムで従業員の立替経費を最小限に抑えれば、経理の人数が少なくても効率的な経費管理が可能に
初期費用と経費精算の処理件数に応じた年額費用で構成される料金体系を採用している点が大きな特徴で、実際の利用状況に合わせた最適な料金を個別に提案してもらえます。従業員は多いけれども利用頻度は少ないといったケースなどではコストの抑制が期待できるでしょう。サポート面では、専任の担当者が導入から定着までを支援してくれるため、システム導入に不慣れな企業でも安心して導入できます。Bill Oneビジネスカードと一体となった経費精算システムにより従業員の立替経費を極限まで減らせ、少人数の経理チームでも効率的な経費精算を実現できる点も、中小企業に向きます。
-

BIZUTTO経費
この製品の特徴サマリ
- 料金は1ユーザーあたり月額440円(100ユーザー契約の場合)。2年目以降は半額の220円になるためコストを大幅に抑制できます
- 従業員30名以下の企業向けには、初期費用0円・月額料金250円〜で通常版と同等の機能を使用できる「ライトパック」も用意されます
- 最大契約ユーザー数の範囲内ならグループ企業の複数法人が1契約で利用可能。2法人目以降は初期費用が不要になるなどのメリットがあります
初期費用11万円+1ユーザーあたり月額440円(100ユーザー契約の場合のモデルケース)で利用開始でき、2年目以降は半額の220円となるため低コストで運用可能です。従業員30名以下の企業向けには「BIZUTTO経費ライトパック」プランが用意され、初期費用0円・月額料金250円〜で通常版と同等の機能を使用できます。最大契約ユーザー数の範囲内ならグループ企業の複数法人が1契約で利用でき、2法人目以降は初期費用が不要だったり、利用料のボリュームディスカウントを受けられたりと費用負担の軽減が可能。企業の規模や成長に合わせた柔軟な価格体系を実現しています。
-
この製品の特徴サマリ
- 基本料金+1ユーザーあたり月額715円の従量課金制で、企業規模や必要機能に応じてコストを抑制しながら導入できます
- 経費精算機能を使用できるのは、「freee支出管理 経費計算Plusプラン」か「freee支出管理 Fullプラン」
- 経費精算ではスマホアプリの自動撮影「魔法スキャン」機能により領収書をかざすだけで経費申請が可能。承認もスマホからいつでも対応できます
利用人数に応じた従量課金制により、スタートアップから中小企業まで、コストを抑えながら導入できるのが特徴です。経費精算機能を使用できるのは、「freee支出管理 経費計算Plusプラン」か「freee支出管理 Fullプラン」。スマホ撮影で証憑を読み取ってすぐ経費申請が可能なほか、承認もスマホからいつでも対応可能です。Fullプランのほうが機能が充実しており、受領請求書データの電子化や受領請求書証憑のフォルダ管理にも対応します。
2.初期費用・月額費用が低価格で導入しやすい
こんな企業におすすめ
- コストを抑えつつ、必要な機能を備えたシステムを導入したい企業
- 一時的に多額の費用が生じることを避け、支出額を安定化させたい企業
- 中小企業やスタートアップで、予算に制約がある企業
このタイプのメリット・デメリット
- メリット
- 初期費用が無料または低価格のため、導入ハードルが非常に低い
- 標準機能がひと通り揃っており、コストを抑えながら業務改善が可能
- 基本的な経費精算機能を必要十分に備えながら、低コストで運用できる構成になっている
- デメリット
- 低価格プランでは機能やサポートが限定的で、柔軟に運用したい場合には対応できないことがある
- 初期費用が抑えられる反面、導入時の支援やカスタマイズ対応が有償オプションとなることがある
- 標準機能に絞った設計ゆえに、特定業種や複雑な承認フローには適合しない可能性がある
導入前に担当者が検討するべきこと

- 自社業務に必要な機能が低価格プラン内でカバーされているか確認する
- 社内教育や初期設定が自社で完結できるかを検討する
- 今後の業務拡大やフロー変更に柔軟に対応できるか評価する
専門家からの選び方アドバイス
低コストで導入できる経費精算システムは、中小企業のデジタル化の第一歩として有効です。ただし、価格の安さだけで選ぶと「必要な機能が不足していた」「サポートが受けにくい」といった問題が生じる可能性もあります。導入前には、自社で必要としている機能をカバーしているか、教育や設定を社内で完結できるかを確認しましょう。将来的な業務拡大も見据え、プランや機能の拡張性もチェックしておくと安心です。
初期費用・月額費用が低価格で導入しやすい経費精算システム一覧
-
この製品の特徴サマリ
- 初期費用・サポート費用0円で導入時のコスト負担を軽減でき、最低利用料金も月額5,500円と安価。中小企業でも予算を圧迫することなく気軽に導入できます
- 1ユーザーあたり月額440円のリーズナブルな料金設定で、小規模チームから利用可能。人数に応じた料金体系により、むだなコストを抑えられます
- 30日間の無料トライアルが用意されているうえ、最低利用期間の縛りもなし。導入(初期設定)サポートプランも用意されていて、経費精算システムに不慣れでも安心
初期費用・サポート費用0円、かつ1ユーザーあたり月額440円、最低利用料金5,500円という低価格で、中小企業でも予算を圧迫することなく気軽に導入できます。30日間の無料トライアルも用意されるほか、最低利用期間の縛りもありません。導入サポートとして設定代行などの各種プランも用意されており、導入担当者が経費精算システムに不慣れでも安心して始められます。
-

MOT経費精算
この製品の特徴サマリ
- 初期費用3万4,650円と月額利用料4,378円で20IDまで利用できるリーズナブルな料金設定
- 1名から利用できるため中小企業でも導入しやすく、月額利用料にサポート保守も含まれるため安心です
- 低価格ながら経費精算・交通費精算・旅費精算・電子稟議(ワークフロー)・自動仕訳など豊富な機能が利用できます
低価格と豊富な機能を兼ね備え、中小企業にも導入しやすい経費精算システムです。初期費用3万4,650円、月額利用料は4,378円で20IDまで利用可能。21ID以上を希望する場合は要問い合わせとなります。月額利用料にはサポート・保守も含まれており、電話やメールで導入まで/導入後のサポートを受けられます。「駅すぱあと」連携による自動経路検索や交通系ICカード取込、会計ソフト連携など、業務をより効率化できる機能も多数備わっています。
3.無料トライアルやデモ体験が可能
こんな企業におすすめ
- 複数のシステムを比較検討中で、一定期間使いながらそれぞれの製品を評価したい企業
- 実際に操作して、自社の業務フローに合うかどうかを確かめてから導入を判断したい企業
- 社内での意思決定や稟議に向けて、操作感や導入効果を具体的に示したい企業
このタイプのメリット・デメリット
- メリット
- 運用開始後の環境に近い形で機能や操作感を確認できる
- 実際の業務に近い条件でのテスト運用が可能なため、稟議資料の裏付けとしても有効
- 使い勝手や導入ハードルを体感できるため、社内の不安を払拭しやすい
- デメリット
- トライアル期間が短く、全機能を十分に試せない場合がある
- デモ環境と本番環境に差異があり、操作感が変わる可能性がある
- 試用後に本契約へ移行しなければ、トライアル期間中に登録した設定やデータがむだになる可能性がある
導入前に担当者が検討するべきこと

- トライアル期間中に確認したい業務フローや重要機能を事前に洗い出しておく
- トライアル期間内での検証に必要な人員・時間を確保し、集中して評価できる体制を整える
- 本契約への移行を前提とした初期設定や導入準備を並行して検討し、移行時のロスを減らす
専門家からの選び方アドバイス
無料トライアルやデモ体験は、経費精算システム導入のミスマッチを防ぐうえで非常に有効です。限られた期間でも実際に操作することで、画面の見やすさや操作性、業務への適合性を具体的に判断できます。重要なのは、単に試すのではなく、評価すべき業務や機能をあらかじめ洗い出し、トライアル期間中に効率よく検証できるよう準備しておくこと。導入を見据えた設定や体制づくりも並行して進めると、スムーズな本稼働につながります。
無料トライアルやデモ体験が可能な経費精算システム一覧
-
この製品の特徴サマリ
- 90日間の長期にわたる無料トライアル期間が設けられており、導入効果を慎重に検証したい企業でも十分な時間をかけて機能性や操作性を確認できます
- 無料体験中の機能制限がなく、AI-OCRを活用した領収書自動読み取りや各種ビジネスチャットツールとの外部連携機など、すべての機能を試せます
- トライアル利用者向けの専用ガイド「お試し期間ToDoリスト」やオンライン相談、問い合わせフォームが用意され、システム導入が初めてでも安心です
90日間の無料トライアルが用意され、期間中は機能の制限なく試せます。AI-OCRによる自動入力から経路検索や運賃の自動計算、ビジネスチャットツールとの連携まで、すべての機能を体験可能です。無料期間が長く、導入前の検証を重視する企業や人員が限られた企業でも安心して検討を進められます。さらに、有意義にトライアルを使うための「お試し期間ToDoリスト」や、困った際のサポートとしてオンライン相談や問い合わせフォームが用意されており、システム導入が初めてでも不安を解消しながら導入判断が可能です。
価格.com編集部が実際に使ってみた使い方・使用感レポートを掲載中
ジュガール経費精算について詳しく見る -
この製品の特徴サマリ
- 無料トライアル期間中は有料プランの全機能を体験できます。トライアル終了時、自動的に有料プランへ切り替わることはないため安心です
- IT初心者でも導入後のスムーズな運用を実現できるよう、電話やメールでのサポート、豊富なマニュアル、ウェビナーなどが用意されています
- 有償の導入支援サービスも用意され、導入から運用開始までに必要な設定を専任の担当者がサポートしてくれます
すべての機能を試せる無料トライアルで、導入前にしっかりと検証ができます。無料期間終了後に有料プランへ自動的に切り替わることはありません。電話やメールでのサポート、豊富なマニュアル、ウェビナーが用意されるなど導入後のサポートが充実しており、システムを使い慣れていない初心者にも安心です。有償の導入支援サービスでは、専任の担当者が導入から運用開始までに必要な設定をサポート。全社展開前のテスト運用や、社内周知から運用開始まで伴走してくれます。
-

rakumo ケイヒ
この製品の特徴サマリ
- 30日間すべての機能を無料で試せる「トライアル」を用意。契約後はそのまま本番環境に移行して継続利用できます
- 初期費用は不要で、料金は1ユーザーあたり月額330円。利用には、Google Workspace(有料版)も別途必要になります
- 共有環境のデモデータで1週間試用できる「オンラインデモ」なら、管理画面は使用できないもののGoogle Workspaceの契約不要で手軽に試せます
すべての機能を30日間無料で試せる「トライアル」が用意されます。経費精算書の作成・提出、交通費の自動計算、Google スプレッドシートとのマスター連携など、使い勝手を実際の使用環境でしっかりと検証できます。Google Workspaceと連携するシステムのため、トライアルの利用でもGoogle Workspace(有料版)の契約が必要です。いっぽう、共有環境のデモデータで試用する「オンラインデモ」なら、Google Workspaceの契約が不要なためより手軽に試せます。
4.中規模以上の企業向けでコストパフォーマンスにすぐれる
こんな企業におすすめ
- 本社・支社・事業所など複数拠点を有し、部門ごとの承認ルートや権限設計が必要な企業
- 組織規模が拡大し、処理件数やユーザー数が年々増加している中堅・成長企業
- 経費精算に限らず、会計・人事・営業支援など各種業務システムとの連携を前提に導入を検討している企業
このタイプのメリット・デメリット
- メリット
- 承認ルートの複雑化や細かな権限設定など、中規模以上の企業の要件にも柔軟に対応できる
- ユーザー数や処理件数が多い環境でも安定稼働し、大量運用時のコストパフォーマンスにすぐれる
- 会計システム・勤怠管理・SFAなど他ツールとの連携機能が豊富で、業務全体の効率化が可能
- デメリット
- 利用料が中〜高価格帯に設定されていることがあり、小規模運用には不向きな場合がある
- 柔軟性が高い反面、初期設定や運用開始までに時間を要することがある
- 連携機能や権限設定が高度な反面、担当者に専門知識や実務経験が求められる
導入前に担当者が検討するべきこと

- 自社の利用規模に対して、どの製品が最も費用対効果にすぐれているかを試算しておく
- 現行の業務フローや会計・人事システムとの連携要件を明確にしておく
- 高度な機能を十分に活用するため、担当者のITスキルや体制の整備が可能かを確認する
専門家からの選び方アドバイス
中規模以上の企業では、単なる価格比較ではなく、自社の業務全体を最適化できるかという視点が重要です。導入時の工数や費用を懸念するよりも、安定稼働や他システムとの親和性、将来的な業務変化への対応力を評価しましょう。特に人事・会計など周辺システムとのスムーズな連携や、運用負担を軽減するための体制構築のしやすさは、長期的な効果を大きく左右します。
中規模以上の企業向けでコストパフォーマンスにすぐれる経費精算システム一覧
-
この製品の特徴サマリ
- 複雑な経費規定や承認プロセス、グループ会社間での異なるルールにも柔軟に対応でき、大手・グループ企業にも最適
- 階層構造でコストセンターを管理することができるため、プロジェクトごと・製品カテゴリごとなどに予算・実績が把握できます
- AIによる効率化や不正検知、高度なセキュリティ、周辺システムとの連携など豊富な機能を備え、大企業の要求にも応えます
複雑な経費規定や承認プロセス、グループ会社間での異なるルールにも柔軟に対応できるほか、階層構造でのコストセンター管理によりプロジェクトごと・製品カテゴリごとなどでの予算・実績が把握できるなど、大手・グループ企業で求められがちな機能を備えます。AI-OCR等による業務の効率化、不正検知によるリスク軽減とガバナンス強化、高度なセキュリティ対策、財務会計・人事給与・購買管理など各種システムとの連携といった充実の機能面により、さまざまな要求に応えます。
価格.com編集部が実際に使ってみた使い方・使用感レポートを掲載中
Spendiaについて詳しく見る -
この製品の特徴サマリ
- 月額料金は3万3,000円からで利用する従業員数に応じて変動するため、企業規模に合わせたコストで利用可能。初期費用は別途11万円かかります
- 大手企業や中小企業、急成長のベンチャーなどさまざまな規模・業種の企業で採用実績があります
- AI-OCR・交通系ICカード連携・自動仕訳・会計ソフト連携など充実した機能を幅広く利用するほどコストパフォーマンスは高まります
料金体系は、初期費用が11万円で月額料金が3万3,000円から。月額料金は利用する従業員の数によって変動するシステムのため、企業の規模に合わせたコストで利用できます。AI-OCR機能による領収書読み取りや交通系ICカード連携による交通費データの取得、自動仕訳機能、主要な会計ソフトとの連携など、便利な機能も充実。大手企業や中小企業、急成長のベンチャーなどさまざまな規模・業種の企業で採用実績がありますが、豊富な機能をより多く活用できるほどコスパが高いと感じられるでしょう。
-

Concur Expense
この製品の特徴サマリ
- 従業員数が数名〜500名ほどの中堅中小企業向けサービスとして「Concur Expense Standard」を用意
- 月額料金は5万円台〜(50ユーザー)で、利用機能やユーザ数に応じて決まります。導入費用は無料です
- 多様なサービスとの連携により経費データが自動で取り込まれ、容易にペーパーレス化を実現できます
- 従業員数が500名以上の企業で、多様な設定が必要な場合は「Concur Expense Professional」が推奨されています
従業員数が数名〜500名ほどの中堅中小企業向けに「Concur Expense Standard」を用意。導入費用は無料で、月額料金は5万円台〜(50ユーザー)、利用機能やユーザー数に応じて決まります。機能面では、QRコード決済アプリやタクシー配車などさまざまなサービスと連携。経費明細を自動で取り込むので、ペーパーレス化を容易に実現できます。スマホで領収書を撮影するとデータが自動入力されるOCRをはじめ、経路検索・定期代控除、会計ソフト連携など、業務効率化につながる機能も豊富です。なお、従業員数が500名以上の企業には「Concur Expense Professional」が推奨されています。
この記事で紹介した経費精算システム
1.従量課金制で柔軟な料金プランを提供
-
 マネーフォワード クラウド経費
マネーフォワード クラウド経費50名以下の法人向けに3プランを用意。基本料金は年額32,736円(ひとり法人プラン)からで、企業規模に応じて選択できます
-
 invox経費精算
invox経費精算基本料金+経費精算を作成した「アクティブユーザー」1人あたり330円が月額料金となる従量課金型のシステム
-
 BillOne経費
BillOne経費利用料金は、初期費用と経費精算の処理件数に応じた年額費用で構成。ユーザーごとに最適な利用料金が設定されます
-

BIZUTTO経費
料金は1ユーザーあたり月額440円(100ユーザー契約の場合)。2年目以降は半額の220円になるためコストを大幅に抑制できます
-
 freee支出管理
freee支出管理基本料金+1ユーザーあたり月額715円の従量課金制で、企業規模や必要機能に応じてコストを抑制しながら導入できます
2.初期費用・月額費用が低価格で導入しやすい
-
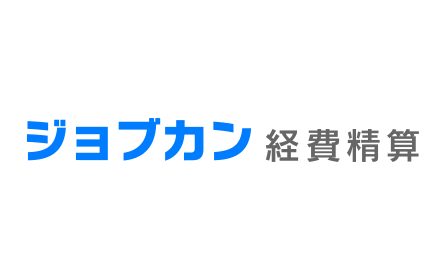 ジョブカン経費精算
ジョブカン経費精算初期費用・サポート費用0円で導入時のコスト負担を軽減でき、最低利用料金も月額5,500円と安価。中小企業でも予算を圧迫することなく気軽に導入できます
-

MOT経費精算
初期費用3万4,650円と月額利用料4,378円で20IDまで利用できるリーズナブルな料金設定
3.無料トライアルやデモ体験が可能
4.中規模以上の企業向けでコストパフォーマンスにすぐれる
他にもこんな経費精算システムを紹介しています
-
- 期間の制限なし、ずっと無料で使えるタイプ
- 期間限定の無料トライアルで全機能が試せるタイプ
- 初期費用0円、もしくは月額コストが安く済むタイプ
- 会計ソフト連携が無料でできる低コスト経費精算システム
-
- AI-OCR特化型:領収書の読み取りとデータ化を自動化
- AIによる不正検知・仕訳自動化型:経理業務の効率化とリスク軽減
- 中小企業向け、コストパフォーマンス重視型:低コストでAI機能を活用
- 交通系ICカードと連携し、交通費の清算が自動化できるタイプ
-
- スマホで撮影した領収書をAI-OCRで自動入力できるタイプ
- スマホでのICカード連携や交通費精算に強いタイプ
- スマホでのチャット連携や通知機能が豊富なタイプ
- スマホで承認まで対応できるタイプ
-
- 【原因:使いこなせず定着しない】操作がシンプルで導入後すぐ使いやすいタイプ
- 【原因:長期コストが高く継続できない】低コスト&スモールスタートが可能なタイプ
- 【原因:システム連携に課題】会計ソフト連携が強く、二度手間を防げるタイプ
- 【原因:サポート不足で挫折】導入時のサポートが充実しているタイプ



