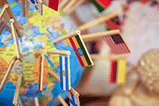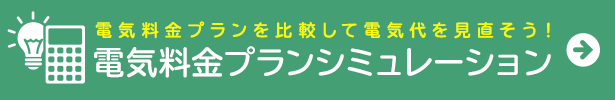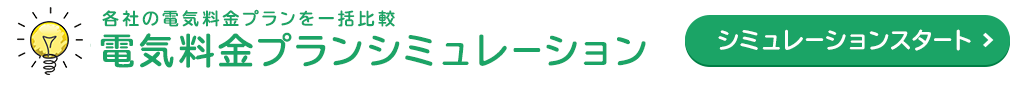更新日:2024年04月17日
真夏と真冬、電気を多く使うのはどっち?

真冬に停電は発生しない?真夏の“節電のお願い”
暑い夏が近づくと、今年の夏の電力供給にどれくらいの余裕があるかといったニュースが目に付きます。状況によっては、“節電のお願い”ということもありました。確かに、部屋に涼しい風を送り続けるエアコンが稼動していると、なんとなくたくさんの電力を消費しているような気になります。しかし、実際に家庭で消費している電力を月ごとに集計すると意外な結果となりました。
季節で変わる一般家庭の電気代
まずは下記の表をご覧ください。2020年から2023年までの二人以上世帯での電気代の平均を月ごとに集計したものです。
二人以上世帯の電気代
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12,232円 | 11,875円 | 12,938円 | 17,190円 |
| 2月 | 13,201円 | 12,854円 | 15,331円 | 18,750円 |
| 3月 | 13,100円 | 13,197円 | 16,273円 | 17,228円 |
| 4月 | 12,117円 | 10,696円 | 13,931円 | 13,617円 |
| 5月 | 10,541円 | 9,644円 | 11,811円 | 11,174円 |
| 6月 | 9,153円 | 8,488円 | 9,990円 | 9,270円 |
| 7月 | 8,585円 | 8,091円 | 9,869円 | 8,627円 |
| 8月 | 9,661円 | 9,774円 | 11,914円 | 10,022円 |
| 9月 | 11,206円 | 10,393円 | 13,202円 | 11,006円 |
| 10月 | 10,152円 | 9,835円 | 12,805円 | 10,780円 |
| 11月 | 8,965円 | 9,103円 | 11,560円 | 9,530円 |
| 12月 | 9,137円 | 9,854円 | 12,514円 | 9,987円 |
| 平均 | 10,671円 | 10,317円 | 12,678円 | 12,265円 |
*総務省統計局の家計調査データをもとに作成
2023年は、電気代の月平均は12,265円ですが、1月から3月は平均額を大きく上回る17,000円以上となっています。夏場は8月・9月でも平均額を超えず、6月・7月にいたっては10,000円以下です。つまり、家庭内では圧倒的に冷房の時季よりも暖房の時季のほうが電力使用量が多いことがわかります。
暖房に電力を多く消費する最大の理由は、外気温と室温の差が夏よりも冬のほうが激しいためです。たとえばエアコンで冷暖房を行う場合、エアコンの設定温度を夏・冬とも25℃として考えてみましょう。冬場の外気温が0℃の場合では室温を25℃高めなければなりませんが、夏場の外気温が35℃の場合では室温を10℃下げるだけです。エアコンは室内を設定温度にするまでの間にもっとも電力を消費するので、温度差が激しい冬場のほうが電気料金は高くなります。また、冬場は夏場と比べて日照時間が短くなるため、照明器具を使用する時間も長くなります。
さらに、冬場は厚着になるので洗濯の回数が夏場よりも多くなる傾向にあります。加えて、洗濯物も乾きにくく、乾燥機を利用している場合は乾燥にかかる時間も長くなります。
季節ごとに違う電気を使う時間帯

それでは、夏場に節電のニュースを見かけるのに冬場に見かけないのはなぜでしょう? その理由は、一日の中での時間ごとの電力使用量の違いにあります。冬場は、朝、学校や会社などの活動が始まると電力の使用が増え、日の入りや気温の低下とともに照明や暖房などでさらに電力の使用量がアップ、17時から19時頃にピークを迎えます。夏場も、活動が始まると電力使用量が増えるのは同じですが、気温の上昇に合わせて電力の使用量がアップし、13時から16時頃にピークを迎えます。冬場は、夏場と比べると昼と夜との電力使用量の差が小さく、1日を通しての電力使用量は比較的フラットですが、夏場は一日の中で時間によって大きく変動します。東京電力の場合、ピーク時の電力需要は夏場のほうが冬場よりも2割程度高くなっています。
電力会社はピークの状態でもしっかりと電気を供給しなければなりませんが、気温が上昇し想定以上に電力の需要が増大すると供給が追いつかなくなる可能性があります。夏場の節電は、ピーク時の電力需要を少しでも緩和するために行っているわけです。