運用方法新NISAで投資信託を選ぶときのチェックポイント
「新NISAで投資信託を選ぶときのチェックポイント」のまとめ
-
- ポイント1
- そもそも投資信託とは?
-
- ポイント2
- どんな資産に投資するかをチェック
-
- ポイント3
- 運用方法はインデックス運用? アクティブ運用?
-
- ポイント4
- 購入時の手数料や信託報酬なども見ておこう
-
- ポイント5
- 純資産額の大きさもチェック
新NISAで広く利用されているのが投資信託です。つみたて投資枠で投資信託の積立てから始めるという人は、しっかり知っておきたいもの。今回は投資信託の基礎知識と選ぶ際のポイントなどを解説します。
そもそも投資信託とは?

投資信託とは、不特定多数の人からお金を集め、その資金をファンドマネージャー率いる運用の専門家チームが株式や債券などで運用し、運用成果を投資した人に分配する仕組みです。投資信託は価格変動リスクがあり、元本保証商品ではありません。
実際には、販売の窓口となる金融機関(銀行・証券会社など)、運用の指図や運用報告などを行う運用会社(投資信託会社)、投資家のお金を管理し、運用会社から運用指図を受けて売買を行う信託銀行の3社が関わってひとつの投資信託が運用されています。そのため、不正などが起きにくい仕組みになっています。
投資信託の仕組み(イメージ)
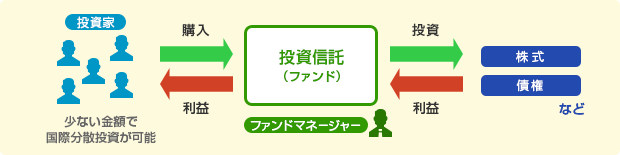
ETF(上場投資信託)やREIT(不動産投資信託)も、資金を集めて専門家が運用するということで投資信託の一種です。ただし、ETFやREITは株式と同じく証券取引所に上場しているため、売買は株式同様に指値なども可能です。
分散投資ができる
投資信託の特徴は株式や債券、不動産、そのほか様々な資産に分散して投資することができ、それによってリスクを軽減することができる点です。株式だけで運用する投資信託であっても、ひとつの投資信託の中に数十から数百の銘柄が含まれているため、個別銘柄の値動きによる影響を軽減できます。
少額でも投資できる
株式投資などを行うには、まとまった資金が必要になります。しかし、投資信託であれば1,000円程度から手軽に投資をすることができるのは大きな特徴です。金融機関によっては100円程度から投資できる場合もあります。
専門家が運用
運用の知識や経験が十分にない状態でも始められるのが投資信託です。海外投資などの経験がなくても、専門家に任せて運用してもらうことができます。ただし、その分の報酬は支払うことになります。
どんな資産に投資するかをチェック

「投資信託は運用の知識や経験が十分にない状態でも始められる」と書いたものの、投資信託(公募投信)は6,000本弱もあります(2023年11月末、投資信託協会資料)。つみたて投資枠で投資できる投資信託は281本(ETF含む。2024年1月現在)、成長投資枠で投資できる投資信託は2,150本(ETF、REIT含む。2024年1月現在)もあり、最低でも自分が投資する投資信託を選ぶ程度の知識は必要です。
まずは、どんな国・地域のどんな資産に投資する投資信託なのかを押さえましょう。
投資対象となる国・地域
投資信託の投資対象となる国・地域は大きく4つに分けられます。国内のほか、海外(先進国・新興国)、全世界があります。それぞれの特徴は下のとおりです。
日本国内で運用するため、為替変動などの影響はありません。身近な投資対象であるため、値動きが把握しやすいのも特徴と言えます。
●海外・先進国
アメリカやヨーロッパ諸国など、経済が成熟した国・地域で運用されます。先進国は今後の高成長は見込めないものの、新興国に比べて政治・経済が安定しているのが特徴です。
●海外・新興国
東南アジアや中東、東欧、中南米など、今後大きな経済成長が期待される国を指します。高いリターンを狙える反面、為替変動リスクやカントリーリスクが高いとされています。
●全世界
全世界を対象とする投資信託には、「オールカントリー」のほか「除く日本」もあります。投資対象に日本を含むかどうかの違いです。
投資対象となる資産
その投資信託を知るには、「何に投資しているのか?」を押さえる必要があります。株式や債券、不動産、コモディティなど、投資対象となる資産にはさまざまなものがあります。
●株式
株式で運用する投資信託は、債券よりも値動きが大きく積極的に値上がり益を狙っていけます。ただし、値下がりリスクもあるので注意は必要です。
●債券
債券で運用する投資信託は、株式と比べて値動きは安定的ですがリターンは小さい傾向があります。ただし、利回りが高く信用格付が低いハイイールド債で運用する投資信託は、ハイリスク・ハイリターンです。
●不動産(REIT)
オフィスビルや商業施設、ホテルなどを所有し賃料収入や売却益を投資家に分配する仕組みの投資信託です。少額でできる不動産投資と考えられ、リスクは債券より高めの傾向があります。
●コモディティ(商品)
金や原油、穀物といったコモディティ(商品)に投資する投資信託もあります。株式などと異なる値動きとなることから、分散投資の効果は高めとされます。また、インフレに強いとも言われます。ただし、価格変動が大きくリスクは高めです。
4つの資産を見てきましたが、これらの資産を複数組み込んだ「バランス型」と呼ばれる投資信託もあります。単一資産のみの投資信託より、リスク軽減を図ることができます。
運用方法はインデックス運用? アクティブ運用?
投資信託の運用方法として、インデックス運用とアクティブ運用があります。それぞれの特徴も押さえておきましょう。
●インデックス運用
インデックス運用とは、市場の平均的な値動きを示すインデックス(指数)と値動きが連動するよう設計された投資信託のことです。信託報酬などのコストが割安なのも特徴です。インデックス運用の投資信託に投資をすることで、その市場を構成する複数銘柄に分散投資ができます。インデックスの例としては、日経225やTOPIX(東証株価指数)、NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数などが挙げられます。
市場の平均的な収益は期待できるものの、目標とするインデックスを上回る収益は狙えません。インデックス運用の投資信託はコストも低く、新NISAつみたて投資枠のような長期積立投資に向きます。
●アクティブ運用
目標とするインデックス(ベンチマークと言います)を上回る成績を目指す運用スタイルをアクティブ運用と言います。日本株式のアクティブ運用の投資信託を例にした場合、日経225やTOPIXなどをベンチマークとして、それを上回る成績を目指して運用します。
ファンドマネージャーをはじめとする運用の専門チームが、市場平均を上回る運用成績を目指して運用するため、インデックス運用よりも信託報酬などの運用コストは高めになります。インデックス運用を大きく上回る運用ができるアクティブ運用の投資信託がある反面、中にはインデックス運用を下回るアクティブ運用の投資信託もあるため、商品選びは重要になります。
購入時の手数料や信託報酬なども見ておこう
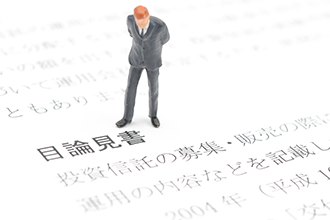
投資信託を選ぶ際には、必ずコストのチェックを行いましょう。
投資信託のコストとしては、保有中にかかる信託報酬はすべての商品でかかりますが、購入時手数料と解約時の信託財産留保額については商品によってかかるものとかからないものがあります。販売会社のWebサイトの商品情報や、目論見書(投資信託の投資判断を行うための重要事項を説明した書類)などで確認しましょう。
●信託報酬
信託報酬は投資信託の運用や資産の管理などに対してかかる費用で、保有している間かかり続けるコストです。投資信託ごとに「年率〇%」と設定されていて、この料率をかけた金額の日割り分が信託財産から日々引かれます。信託報酬は、投資信託の販売・運用に関わる販売会社、運用会社、信託銀行の3社へ支払われます。
新NISAつみたて投資枠で選定されている投資信託では、信託報酬は一定水準以下に限定されています。具体的には、国内資産を対象とするインデックス投信は上限0.5%(税別)、内外・海外資産を対象とする投信は上限0.75%(税別)と、低水準に定められています。
●購入時手数料
投資信託を購入する際に販売会社に支払う手数料。かかる商品とかからない商品があり、かかる商品は「購入代金の〇%」と設定されていて購入時に支払います。購入時手数料がかからないノーロード型の商品も多くあります。また、同じ商品でも販売会社によって購入時手数料が異なる場合もあります。なお、新NISAつみたて投資枠に選定されている投資信託は、すべてノーロード型です。
●信託財産留保額
投資家が中途換金をする際には、運用中の資産の一部を売却するなどして資金を捻出することもあるため、解約時にこうした費用が設定されている投資信託があります。「解約代金の〇%」とされています。徴収された分は、運用資金(=信託財産)に留保されるため、この名称となっています。信託財産留保額はかからない投資信託も多いですが、念のため確認をしましょう。
純資産額の大きさもチェック
投資信託の純資産額は、その投資信託の規模を表します。投資信託を選ぶ際には、この純資産額もチェックをする必要があります。純資産額がおおむね100億円以上の投資信託であれば通常は問題ありませんが、純資産額が小さいと、運用期間満了前に繰上償還となる可能性もあります。
繰上償還とは、当初の運用期間満了を待たずに運用を打ち切ることです。売却益が出るタイミングならまだしも、売却損が出る状態での繰上償還は損失確定となってしまいます。そのような事態を避ける意味でも、投資信託を選ぶ際には、目論見書に記載されている繰上償還の条件となる純資産額がどれくらいなのかを必ず確認しましょう。
また、純資産総額が右肩下がりに減る傾向が現れていないかも確認しておきましょう。何らかの理由で投資信託の解約が増えている状況がある場合は要注意です。今は問題ないとしても解約が続けば、いずれ繰上償還のラインに届いてしまう可能性もあるからです。
新NISAを始める際には、投資信託の商品選びをしっかりと行いたいものですね。
- 執筆・監修 豊田眞弓(とよだ まゆみ)

- FPラウンジ代表、亜細亜大学非常勤講師。AFP。マネー誌ライターなどを経て、独立系FP。講演・講師、コラム執筆や監修、個人相談などを業務としている。ライフワークとして、30年近く子どもから社会人、高齢者までの金融経済教育に携わってきた。FP技能士3級講座講師も務める。趣味は講談、投資。
- 投資信託を選ぶときのポイントを理解したら、NISAを扱っている金融機関を見てみよう
「価格.com NISA口座比較」 ご利用上の注意
- 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。
- 掲載している商品やサービス等の情報は、各事業者から提供を受けた情報または各事業者のウェブサイト等にて公開されている特定時点の情報をもとに作成したものです。
- 最新の情報が反映されていない場合がございます。最新情報は各証券会社の公式ページ等でご確認ください。
- ご契約にあたりましては、必ず金融機関において「契約締結前の交付書面」等をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。
- キャンペーン・特典は各広告主において実施されるものであり、広告主による募集要綱等を十分にご確認ください。
- 当社では各金融機関のサービスに関するご質問にはお答えできません。各金融機関にお問い合わせください。



