
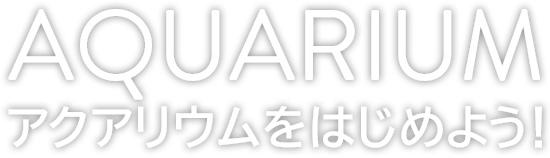
水面に油膜が出現、なぜ?
水槽に発生した油膜(ゆまく)。その正体とは? 対策方法も知っておきましょう。

油膜の正体とは……
魚を飼育していると、水面が妙に白っぽく見える、あるいは油のように虹色に光っていたり、緑色っぽくなっていたりすることがあります。指でかき回すと壊れ、水面は膜状に何かが広がっていることがわかります。アクアリストの間ではこれを油膜(ゆまく)と呼んでいます(実際に油であるといっているのではなく、水面に漂う油のように見えるという意味)。
見た目が悪いのはもちろんですが、これが広がっていると水中と空気のガス交換が妨げられ、魚の生活環境が悪化する恐れもあり、昔から嫌われています。これまで、油膜の正体や発生原因はさまざまに議論されてきたのですが、諸説ある状態で、明確なことはわかっていません。以下、4つの説を見ていきましょう。
①油脂説
ダイニングキッチンなどに水槽を設置しているとき、調理の油が空気中から水面に落ちる、あるいは餌に含まれる油脂が溶けるなど、なんらかの油が水槽に入って膜になるという説です。昔はそれなりにいわれてきた説なのですが、最近ではそれもほぼなくなりました。そもそも油脂による膜は流動性が高く、指でかき回して壊れることもないため、水槽の水面で「壊れる油膜」は油脂ではない、と判断できます。
②バクテリア説
繁殖したバクテリアやその死骸によるコロニーが水面に膜をつくるという説です。自然界でも鉄バクテリアが膜をつくることが知られています。水たまりなどに浮く油膜がそれで、湿原などにできると薬品の流出事故と間違われることがあります。水槽でも同じようになんらかのバクテリアが膜をつくっていると考えられており、有力な説の1つになっています。
③藻類説
バクテリアと同じように、藻類が膜状に繁殖しているという説です。原因となる藻類は藍藻類の一種とされることが多いのですが、珪藻によるものもあるようで、明確ではありません。油膜が緑色に見える場合、藍藻などの藻類による可能性が疑われます。ただし、珪藻は一般に茶色なので、その場合は色だけで判別することはできません。
④有機物説
おそらく、最もメジャーな説でしょう。水中には魚のフンなどに由来するタンパク質が漂っていますが、これは通常であれば微生物によって分解されていきます。しかし、過密飼育やろ過能力不足などにより、処理が追いつかないと、これらの有機物が水面に浮いて油膜をつくる、と考えられています。
有機物由来の油膜は水質悪化のサインとされており、水槽の環境改善が必要な目安として挙げられることもあります。水槽だけでなく施設養殖においても、過密飼育により油膜が発生するという報告があるので、実際に有機物が油膜の原因である可能性は十分に高いと考えられます。
以上のとおり、4つの説がありますが、油膜といっても性質や見た目が異なるパターンが多々あり、実際の正体はそれぞれ違っていたり、複合的であったりすると思われます。

エアポンプとエアストーンを利用してエアレーションを行うと、水面が波立つので、油膜が除去されやすくなります。あわせて、水槽環境やろ過能力などの見直しを検討するとよいでしょう。
どのように対策する?
油膜をなくすにはどうすればいいのでしょうか? キッチンペーパーで吸い取るという方法もありますが、お手軽なこの方法はたいがい挫折することとなります。効果が一時的なもので、翌日には油膜が再発してしまうからです。
水面をかき回す
油膜は触ると壊れます。案外もろいものなので、ろ過装置(フィルター)の水流で水面を回したり、シャワーパイプの排水が水面を巻き込むように設置したりすることで、油膜を除去することができます。エアレーションでも同様の効果があり、油膜をなくすこと自体はそれほど難しくありません。
ただし、この方法は物理的に油膜を取り去っただけで、油膜の発生源を除去したわけではなく、再発の可能性も高いままです。そのため、油膜を除去すると同時に、水槽の環境改善にも取り組むことが大切です。油膜は水質悪化により発生することが多いため、まずは水質の改善から対処を進めていきましょう。
過密飼育になっていませんか?
水質悪化の最も疑われる原因は過密飼育です。あれもこれも飼育したい、誘惑には逆らえない、というのもわかりますが、まずは衝動的に魚を飼う(買う)ことをやめ、計画を立てて飼育魚を絞る、水槽サイズに見合った匹数に抑える(目安として魚の体長1cmあたり飼育水1リットル)、などの対策が必要です。
また、餌の量が多すぎると魚も排泄物が増え、油膜の原因になることがあります。魚たちが水槽の前で餌をねだっていると、ついつい甘やかしてたくさん与えたくなるのですが、過剰な餌やりは魚にとっても水槽の環境にとっても、よいことはありません。改めて水槽をじっくり観察し、魚がぶっくりと太っているようであれば、日々の給餌量を抑えてみましょう。
ろ過能力を見直してみよう
ろ過能力が不足して水槽の水が汚れることで油膜の発生につながっている可能性もあるため、フィルターのパワーアップを検討します。処理能力が高い大きなフィルターに交換する手もありますが、サブフィルターとしてエアーリフト式の小型フィルターを投入すると、水面をかき回す効果と併せて油膜対策に有効です。
油膜が出ない環境とは?
そもそも油膜を発生させない環境とはどのようなものでしょうか? これはこのアクアリウムの趣味とは相反する部分もあるのですが、シンプルライフを心がけることです。とにかく欲張ったり詰め込んだりしない、魚の数を絞り、ゆったりとした飼育環境を整えましょう。もちろん、日々のメンテナンスもしっかりと行います。枯れた葉や死んでしまった生体はすぐに取り出し、水槽内に余計なものを残しておかないようにして、水槽内の環境に負荷をかけないようにします。このような「余裕のある水槽」は、油膜も発生しにくくなります。
-
アクアリウムのメンテナンス
-
こんなときはどうする?
トラブルシューティング
- ペットカテゴリ
- 熱帯魚・アクアリウム用品
- 水槽
- 水槽用フィルター
- 水槽用照明
- 水槽用保温・保冷器具
- 水槽用エアレーション用品
- 熱帯魚・アクアリウム用エサ
- 水草
- その他の熱帯魚・アクアリウム用品
- 価格.comホーム
- ペット
- アクアリウムをはじめよう!価格.com
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止



