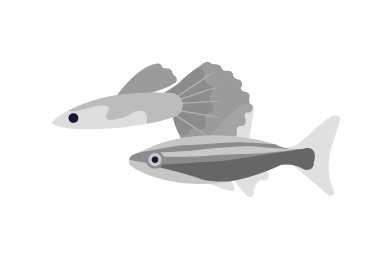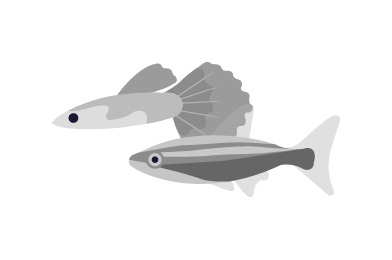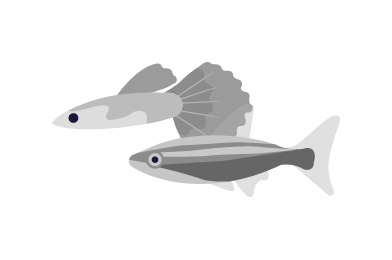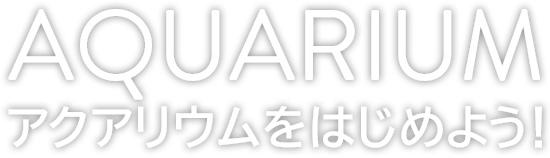
水草を美しく繁茂させるには?
水草を美しく育てて繁茂させるには、さまざまな要素をバランスよく揃える必要があります。

水草を育てるために必要なもの
水草を育てるために必要な要素はさまざまですが、特に重要なのは「光」「温度」「肥料」「二酸化炭素(CO2)」、そして生活場所である「水」、根を張るための「底床(ていしょう)」です。これらの環境が1つでも整っていない水槽では水草栽培は難しくなってきます。しかし、だからといって光や肥料をガンガン投入して「物量勝負だ!」といった状態になると、かえって水草には害になる恐れもあります。これらの要素をバランスよく揃えておくことが、水草育成を成功させるポイントとなります。
植物にとっての光
ご存じのとおり、植物は光を使って光合成を行います。植物にはアンテナ色素という電磁波(光)を受け止める色素があり、これを使って光をエネルギーに変え、二酸化炭素から有機化合物をつくり、自身を成長させたり、生理作用を維持したりしています。そのため、植物は光合成を行うために必要な光量がなくては生きていくことができません。
植物にとって光は重要ですが、必要とする光の量は水草の種類によって違います。強光を好む水草に十分な光を与えなければ成長は悪くなり、逆に陰性水草の場合、強い光を当てても無駄になるばかりか、害になることもあります。
というのも、植物は当てた光をすべて利用できるわけではないからです。とくにアヌビアスやミクロソリウムなどの陰性水草は弱光に適応しているため、強い光を当てても光合成が飽和状態になってしまい、無駄な光エネルギーは活性酸素を発生させ、水草の細胞にダメージを与えてしまうことがあります。もしくは、代謝が遅い陰性水草は強い光を十分に利用できず、藻類(コケ)のエネルギー源となってしまう恐れがあります。そのため、照明の光量(強さ)は植物の種類と相談して決める必要があります。
1つの水槽で複数の水草を植栽する場合、まずは好む光環境が近い水草の種類を揃え、その条件に合わせて照明を用意するとよいでしょう。水草図鑑をめくると、各水草について必要な光量の目安が書かれていることが多いので、事前に情報を集めておくと安心です。
また、水草は光を長時間当てれば育つ、というわけではありません。無駄な長時間照射は藻類(コケ)を育て、相対的に水草を弱らせてしまう恐れもあります。もちろん、短すぎても成長に影響を与えるので、1日7〜8時間程度を基本とし、極力タイマーを使って毎日の照射時間を一定に保つとよいでしょう。
適温を維持しよう
植物は自分で体温を調整できず、生活場所の水温に左右されて生きています。そして、低温も高温もどちらもあまり好きではありません。低温については国産水草などでは耐性もありますが(冬に休眠する種類を除く)、これらは低温耐性遺伝子を発現させることで寒さに対応しているためです。一方、熱帯産水草の多くは低温耐性を持っていないため、低温では生きていくことができません。多くの熱帯魚と同様、適切な温度(25度前後)を維持することが大切です。
各水草の生育地域により適温は異なるのですが、特に夏場など、水槽が高温になる時期は、水草にとっても鬼門となります。まず、水温が上がると水中の溶存気体濃度が減る、という問題が生じます。同時に光合成の材料となるCO2が減ることになり、光をいくら照射しても光合成の効率が上がらなくなるのです。
また、植物体内でも光合成に問題が出てきます。光合成中枢はCO2だけでなく、わずかですが酸素とも反応します。高温になると酸素との反応が増え、光合成の効率が悪くなってしまうのです。C4光合成植物のように光合成中枢でCO2を濃縮してこの問題を回避できる植物もありますが、多くの水草は高温が苦手です。そのため、夏場は水槽用冷却ファンやクーラーを使用して、水温を下げる必要があります。目安として、熱帯魚よりやや低めの水温(22〜24度)を維持すると、夏場でも水草が調子よくキープできるでしょう。

水草をたくさん植栽する場合、二酸化炭素(CO2)の添加が不可欠です。写真の水草水槽では、右側面に二酸化炭素の拡散器を設置しています。
二酸化炭素(CO2)の添加
前にも述べたとおり、CO2は光合成の材料になるので、水槽の中にCO2がないと水草は生きていくことができません。CO2を人工的に添加することで、光合成が活発になって水草がよく育つことは間違いないのですが、実はそれほど単純なものではありません。CO2の影響は多岐にわたります。順に見ていきましょう。
まずCO2は、水に溶けると炭酸水素イオンと遊離の二酸化炭素に分かれる、という性質を持ちます。その比率はpHに依存し、水温24度、pH6.4くらいで両者がおよそ半々、アルカリ性に傾くほど炭酸水素イオンが増え、酸性に傾くほど遊離の二酸化炭素が増えます。そして、水草の多くは遊離の二酸化炭素しか吸収できません。炭酸水素イオンが9割以上にもなるpH8の環境では、水草の多くが光合成をあまり行うことができなくなります。そのため、水草栽培においてはpHの調整が必要になりますが、CO2は水に溶けるときに水素イオンを放出するため、CO2添加を行うことで、pHを酸性に傾ける作用が期待できます。水槽に「pHモニター」を設置することで、pHの常時変化を測定できるため、管理が非常に楽になります。
炭酸水素イオンを利用できる水草と利用できない水草
水草の中には炭酸水素イオンを利用できる種類も存在しています。このような水草は弱アルカリ性でも支障なく光合成を行えるため、栽培が容易です。一般的に水中適応度の高い水草、例えばバリスネリアのように水中のみで生活する水草はこの能力を獲得しています。この件に関して、静岡農業高校生物部が興味深い発表を行っているため、参照先をリンクします。
この発表によると、植物は藍藻(らんそう)が獲得した「炭酸水素イオン利用能力」を引き継ぎ、緑藻類から陸上植物へと進化し、陸上に出た段階で不要となった「炭酸水素イオン利用能力」を失った、と推測しています。そして植物が再び水中に戻ったことで、この利用能力を再獲得したとのことですが、これは水中適応度の高い水草が「炭酸水素イオン利用能力」を持っていることを裏付ける、説得力の高い説といえます。
先に水草の育成において水温や強光による影響について解説しましたが、CO2添加はこれらを緩和します。CO2濃度が高い状態では植物は効率的に光合成を行うことが可能となり、光エネルギーを思う存分使えるようになります。また、高温下においてもCO2濃度が高い場合は酸素と光合成中枢が結びついてしまう問題を軽減できます(CO2の濃度が高いときはCO2と結びつきやすくなるため)。
そもそも光合成は、地球が高いCO2濃度であった時代に誕生した反応過程です。CO2を人工的に添加することにより、植物が本来の能力が発揮できるようになる、ということもできます。以上の理由から、水草育成のために水槽にCO2を添加することは水草栽培の要であり、大きなメリットがあるのです。水槽にCO2を添加するためには、レギュレーターや拡散筒、CO2ボンベなど、初期コストがある程度かかってしまいますが、水草の栽培をメインに据えるのであれば、導入するべきでしょう。
CO2を添加しても水草が育たない
CO2を添加してもうまく水草が育たない場合、まずはその添加量を疑ってみましょう。水槽サイズ(水量)に対してCO2が少量であれば効果は十分に発揮できません。また、これまで述べてきたとおり、pHも重要です。アルカリ性に傾いていた場合、いくらCO2を添加しても水草が利用できません。特に光合成が盛んな日中はCO2が消費され、飼育水のpHはアルカリ性に傾きやすくなります。この場合、CO2添加量を増やす、またはソイルなど弱酸性の軟水をつくる底床を導入する、pH調整剤を利用する、などpHを弱酸性に誘導することを考えるとよいでしょう。ただし、CO2の過剰な添加は、魚やろ過バクテリア、原生動物など微生物にとっても有害で、水槽環境を壊してしまう恐れがあるため、まずはpHを弱酸性にキープすることが大切です。
なお、CO2添加は照明が点いていないときに行うと、水槽内の生物にダメージを与えてしまいます。電磁弁とプログラムタイマーを利用し、照明ONから1時間程度後に添加開始、照明OFFの1時間程度前に添加終了の設定を行うとよいでしょう。
CO2は逃げやすい
せっかく添加したCO2ですが、フィルターのシャワーパイプなどの曝気(水を空気中にさらすこと)で失われると、本末転倒になります。CO2は溶けやすく逃げやすい性質を持ちます。曝気を行うと、CO2は空気中に逃げていってしまうのです。そのため、水草育成(レイアウト)をメインとする水槽では、密閉式の外部式フィルターが最も望ましく、排水時も空気を巻き込まないように設置する(パイプを水中に備える)必要があります。

水草の肥料は不足している成分を見極め、過剰にならないように添加することが大切です。
肥料(水草栄養素)
肥料は水草がさまざまな体の構造を作るのに利用されるほか、体内の生理作用のために使用される、必要不可欠な無機栄養素です。そのため、水槽内(水中・底床)で肥料が尽きると、水草は成長できなくなります。肥料といってもその種類は多く、植物が必要とする量もそれぞれ異なります。
大量要素
水草が最も多く必要とされるのは窒素(N)、リン酸(P)、カリウム(K)です。これらは「大量要素」とも呼ばれ、このうち窒素は体の葉緑体など構造物を作る基本材料となります。ろ過の最終生成物である硝酸塩がこれにあたります。環境にもよりますが、水草が大量に植栽されていなければ、不足は起こりにくい成分です。
リン酸は代謝に必要な成分で、根や茎の成長、開花や結実に強く影響しますが、葉を観賞する水草ではあまり重視されておらず、リン酸は藻類の元になりやすいことから控える、というのが水草栽培のセオリーとされています。
カリウムは光合成や浸透圧調整などさまざまな機能に影響する肥料で、水槽では不足しがちでです。そのため、水草栽培ではカリウムの施肥が中心に行われています。
中量要素
次に必要とされる成分は、「中量要素」といわれるカルシウム(Ca)、マグネシウム(Mg)、硫黄(S)です。しかし、水草栽培ではむしろカルシウムやマグネシウムなどの硬度に影響を与える肥料分は控えめにするのがセオリーとされ、あえてこれらを施肥することは多くありません。
微量要素
鉄(Fe)、マンガン(Mn)、ホウ素(B)、亜鉛(Zn)、モリブデン(Mo)、銅(Cu)、塩素(Cl)といったごく微量ではあるものの、植物にとって必要な肥料分で、「微量要素」と呼ばれます。ただし、これらの多くは土壌や水道水にも含まれているため、定期的な水換えを行っていれば、あまり不足することはありません。例外として、鉄は微量要素のなかでも要求量が多めです。クリプトコリネなど鉄分の要求量が多い水草も存在します。そのため、あえて鉄肥料だけを追加で与えるケースもあります。
肥料の与え方
有茎水草は水中から肥料をよく吸収するため、市販の水草用液肥(液体肥料)が向いています。根をよく張るロゼット型の水草は、土壌に固形肥料を埋め込むのが一般的です。もちろんこれは有茎草にも使えます。このタイプは水中への肥料流出が少なく、藻類の原因になりにくいというメリットがあります。ただし、即効性がないため、ゆっくり効果が現れてきます。
肥料は与えればよい、というものではありません。過剰な肥料は水草に害をおよぼします。もっとも水槽の場合、水草に過剰症状が出るというより、藻類(コケ)の大発生を招くことが多いでしょう。藻類の発生が制御不能になった場合、過剰な肥料を疑い、水換え頻度を上げて肥料分を水槽外に出すことが大切です。
一方、肥料が少ないときは水草に症状が現れます。葉が妙に小さい、葉の色が薄いときは窒素不足を疑います。リン酸は成長部に作用するので、新芽の立ち上がりが悪い、根の張りが少ないときはリン酸不足を疑います。さらにカリウムが不足したときは下葉が落ちるなど、成長部以外に害が出やすくなります。
窒素、リン酸などの不足が疑われる場合、これらの成分を含む総合肥料(「カミハタ OKOSHI」など)を試してみるとよいでしょう)。カリウムだけを追加したい場合、カリウム専用肥料が便利です(「テトラ クリプト」など)。鉄が不足すると、葉に筋状の模様が出たり、部分的に色が薄くなったりする症状が現れます。その場合、鉄分専用肥料を投入するといいでしょう(「テトラ イニシャルスティック」や園芸用の「メネデール」など)。鉄分はpHが中性よりアルカリ性に傾くと吸収されにくくなるため、あわせてpHのチェックも行い、弱酸性をキープすると万全です。

スターレンジ(トニナ属)。南米産の水草は酸性度が強い水域に生育しており、特にアルカリ性の環境には弱いことが知られています。
水質 水道水の水質を知っておこう
CO2の解説にあるとおり、水草を調子よく育成するために水質はとても大切です。とくにpHは炭酸水素イオンを利用できない種類が大半の水草にとって、死活問題です。硬度の高い水では酸性を保ちにくいため、水草育成では硬度の低い弱酸性の軟水が理想です。まずは水道水の水質をチェックしておきましょう。
日本の水道水はほとんどの地域で「中性の軟水」であるため、魚の飼育や水草育成に関しては恵まれた環境です。ヨーロッパでは硬水の地域が多いため、水作りには大変な苦労をされているようです。しかし、日本国内でも、沖縄や石灰質土壌の地域では水道の硬度が高い傾向にある地域もあるため、注意が必要です。そこで、お住まいの地域の水道局ホームページにアクセスし、水質データを探してみましょう。硬度の数値が見つけられるはずです。多くの地域は「50〜60mg/L」程度かそれ以下の軟水ですが、沖縄では「100mg/L」を大きく超える地域もあります。
水道水の硬度が高い場合、ゼオライトやイオン交換樹脂を利用し、軟水化を行うとよいでしょう。これらはイオン交換によって硬度を下げる効果があります。ただし効果は有限なので、定期的に樹脂の交換が必要となります。もしくはソイルや赤玉土を使用することで、簡単に軟水をつくることができます。もちろんこちらも効果は有限となるため、こまめに水質をチェックする必要があります。
撮影協力店
執筆
赤沼敏春 Toshiharu Akanuma
田形正幸 Masayuki Tagata
-
アクアリウムのメンテナンス
-
こんなときはどうする?
トラブルシューティング
- ペットカテゴリ
- 熱帯魚・アクアリウム用品
- 水槽
- 水槽用フィルター
- 水槽用照明
- 水槽用保温・保冷器具
- 水槽用エアレーション用品
- 熱帯魚・アクアリウム用エサ
- 水草
- その他の熱帯魚・アクアリウム用品
- 価格.comホーム
- ペット
- アクアリウムをはじめよう!価格.com
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止